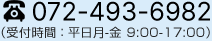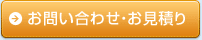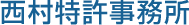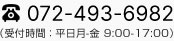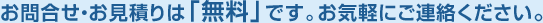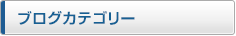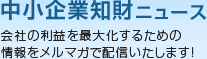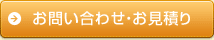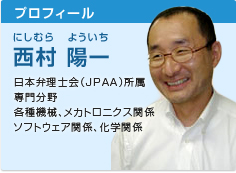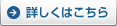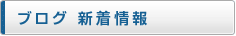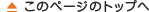商標権侵害 賠償額を増額 大阪高裁「堂島ロール」訴訟
2013.03.26 10:00
神戸市の洋菓子メーカー「ゴンチャロフ製菓」が自社商品「モンシュシュ」と同じ名称をマークに使われたとして、「堂島ロール」で知られる大阪市の洋菓子製造販売会社「モンシェール」(旧モンシュシュ)にマークの使用差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が7日、大阪高裁であった。小松一雄裁判長は「モ社はマークの名称を変更した」として差し止め請求を棄却したうえで、1審判決後も商標権侵害の期間があったことから、賠償額を約5100万円に増額した。
2011年6月の1審・大阪地裁判決は、モ社の商標権侵害を認め、包装紙や看板マーク使用を禁止し、約3500万円の賠償を命じていた。
判決では、ゴ社は1981年、仏語で「私のお気に入り」を意味する「モンシュシュ」を商標登録し、チョコレートの名称にした。モ社は2003年に設立後、モンシュシュのマークを使用してきたが、昨年7月、「私のいとしい人」の意味の現屋号「モンシェール」に変更し、これに合わせてマークも変えた。
読売新聞 2013年3月8日 朝刊本件は、他人の権利を尊重しなければ、痛い目に遭うということを如実に示しており、事業者はこれを教訓としなければならない。
事業者が社名や商品名を決定する際は、商標調査を行い、他人の商標権を侵害しないような名称を選択すべきである。そして、決定した名称については直ちに商標出願を行い、名称使用の初期段階で登録しておくべきである。
モンシェール社のように、有名になったときに権利侵害として訴えられ、名称を変更しなければならないリスクと、権利取得に要する費用とを考慮すると、「有名になってから登録すればよい」という考えは捨てたほうがよいといわざるを得ない。
弁理士 西村陽一
中国における権利行使
2013.03.20 10:00
中国における知的財産権侵害に対する権利行使は、行政機関に求める行政救済ルート(行政摘発)と裁判所に求める司法救済ルート(民事訴訟)の二つのルートが存在する。利用頻度が高いのは行政取締りであり、2010年では、行政機関への取締要請2,972件中、行政摘発件数は2,631件であった。ちなみに、2009年の民事訴訟提起件数は32件であった。
<行政救済ルート>
●代表的な行政取締り機関
・地方商工行政管理局(AIC)
商標法及び不正競争防止法に基づき取締りを行う。
商標権侵害
知名商品特有の名称、包装、装飾の模倣品
・地方質量技術管理局(TSB)
製品質量法を根拠に、消費者保護の観点から模倣品取締りを行う。
原産地の詐称、他人の工場名・工場住所の詐称・盗用など
偽物の混合、偽物を本物と代替するなど
・海関
模倣品の海外輸出を取締りを行う。
・知識産権局(IPO)
専利法に基づき取締りを行う。
特許権侵害、意匠権侵害、実用新案権侵害は、国家知識産権局(SIPO)の下部機関である地方知識産権局(APPA)が取り扱う。
<司法救済ルート>
●司法機関
中国の司法機関である人民法院は、「最高人民法院」、「高級人民法院」、「中級人民法院」、「基層人民法院」から構成される。
中国では、日本の「三審制」とは異なり、「二審制」が採用されており、知的財産権の侵害事件は、通常、中級人民法院が第一審となり、上級審にあたる高級人民法院が第二審(最終審)となるが、重大な影響を及ぼす事件は、高級人民法院を第一審とすることができる。
<行政救済ルートと司法救済ルートの比較>
行政ルート(AIC,TSB)〔商標権侵害〕、行政ルート(IPO)〔特許権・実用新案権・意匠権侵害〕及び司法ルート〔民事訴訟〕を比較すると、以下の通りである。
1.処罰
・行政ルート(AIC,TSB):模倣品の没収・廃棄、製造販売行為の停止、罰金
・行政ルート(IPO) :侵害行為の停止命令、損害賠償の調停
・司法ルート :損害賠償(強制執行可能)、侵害の停止
2.時間
・行政ルート(AIC,TSB):比較的早い(1~6か月程度)
・行政ルート(IPO) :訴訟よりは早い
・司法ルート :長時間を要する(一審は1年程度、二審は半年程度)
3.費用
・行政ルート(AIC,TSB):比較的安価(50~100万円前後)
・行政ルート(IPO) :訴訟よりは安価
・司法ルート :高価(数百~一千万円程度)
4.手続
・行政ルート(AIC,TSB):比較的簡単
・行政ルート(IPO) :訴訟とほぼ同様
・司法ルート :難しい
5.証拠
・行政ルート(AIC,TSB):比較的厳格ではない
・行政ルート(IPO) :訴訟とほぼ同様
・司法ルート :厳格に制限される
中国進出時の失敗事例(3)
2013.03.13 10:00
●技術ノウハウ関連
・引き合いがあり、技術資料を渡したら、その後進展がなく、模倣品が出た
・展示会でカタログを配布したら、模倣品が出た
<対応策>
営業秘密の管理を徹底することが重要。
中国における営業秘密の認定要件は日本と概ね同じであり、営業秘密として法的保護を受けるためには、以下の3要件を満足する必要がある。
[ 営業秘密としての認定要件 ]
1.公知でないこと
その情報が公開ルートから直接得ることができないことが必要。
具体的には、
①営業秘密の所有者が主観的に秘密保持の意思を備えていること
②営業秘密が客観的に公衆に知られていないこと
2.権利者に経済的な利益をもたらすことができ、実用性があること
①価値性
経済的価値、即ち、権利者に現実的または潜在的な経済的利益または競争の優位性をもたらす価値を有していることが必要。
→現実に存在する経済的価値と、繊細的な価値の双方を含む
→所有者が実用的価値を認識するだけでなく、客観的に見ても実用的価値を備えていなければならない
②実用性
その内容としての技術情報及び経営情報が生産及び経営において応用でき、かつ積極的な効果を生むことができなければならない。
3.権利者が秘密保持措置を講じること
その情報を客観的に秘密として管理していると認識できる状態にあることが必要。
具体的には、
①情報にアクセスできる者を特定すること
②情報にアクセスしたものが、それを秘密であると認識できること
従って、
① 秘密保持契約をしないで秘密情報を渡すと、公開されても文句は言えない。
② 展示会で技術資料を配布すると、営業秘密ではなくなる。
③ リバースエンジニアリングできるような技術は営業秘密に当たらない。
④ ノウハウの流出を懸念して日本だけに特許出願をしても、海外から自由に閲覧することができるので、ノウハウは出願せずに秘密に管理するほうがよい。
中国進出時の失敗事例(2)
2013.03.06 10:00
●知的財産登録関連
・特許、実用新案、意匠に関し、日本国内で出願または権利取得しているが、中国で登録ができない
・中国国内で知的財産権を取得していないので、ライセンスできない
・中国国内で知的財産権を取得していないので、模倣品対策ができない
<対応策>
中国進出企業は、『知的財産権を取得するには、種々の要件を満足する必要がある』ことを認識しておくことが重要。
① 属地主義
特許権、意匠権、商標権等の知的財産権は各国毎に権利が発生し、その権利は、その国の国内だけで有効である。
→日本国で取得した知的財産権の効力は中国国内に及ばない。
② 先願主義
技術やデザインについての独占権(特許権・実用新案権、意匠権)取得に関し、殆どの国においては、同一の技術、同一・類似のデザインについて先に出願した者に権利が付与されるという先願主義が採用されている。
→発明が完成していても競合他社に先に出願されてしまうと、同一発明について特許権を取得することできなくなる。
③ 新規性(世界公知、新規性喪失の例外)
技術やデザインについての独占権を取得するには、その技術やデザインが世界的に新規である必要がある。
→自らが日本国内で公にした技術やデザインについては、中国で特許権や意匠権を取得することができない。公表前に各国で出願しておくのが原則。
ただし、新技術を展示会に出展したり、業界紙に掲載した場合は、所定の条件下、新規性を喪失しなかったものとみなされる場合があり、その場合は、所定期間内に出願が認められる。
→新規性喪失の例外規定の適用条件は各国毎に異なるので、注意を要する。
④ パリ条約上の優先権を主張した外国出願
日本国内に出願した後、1年以内にパリ条約上の優先権を主張して外国に出願すると、日本出願と同日にその国に出願したものとして取り扱ってもらえる。
→外国への出願準備期間を考慮すると、日本出願後、数か月以内に外国出願を行うか否かの決定をしなければならない。
⑤ 国際出願
日本国特許庁に国際特許出願をすると、その出願日に世界各国に出願したものと認められる。ただし、出願後30か月(2年6か月)以内に権利取得を希望する国への移行手続き(その国の公用語に翻訳した出願書類を提出する手続き)を行わなければ、その国については、出願が取り下げられたものとみなされる。
→パリ条約上の優先権を主張した外国出願する場合に比べて、外国での権利取得の検討期間を延ばすことができる(メリット1)。
→日本国特許庁が作成する国際調査報告を受け取ることができるので、各国における権利化の可能性を事前に判断することができ、各国に移行すべきか否かの指針とすることができると共に、その後の戦略を策定することができる(メリット2)。
→通常の日本出願に比べて費用が高い(デメリット)。
中国進出時の失敗事例(1)
2013.02.27 10:00
●現地販売代理店関連
・現地販売代理店に商標登録を任せたら、代理店名義で商標登録されてしまった
<対応策>
中国語で記載された書類に闇雲に署名、捺印しない。
出願権の譲渡証と出願の委任状とでは意味が全く違うので、書類の内容を確認した上で捺印することが重要。
※出願権の譲渡証に署名、捺印してしまうと、取り返しのつかないことになる。
・販売代理契約に商標使用の約定がないため、商標を勝手に使われてしまった。
<対応策>
看板、カタログ等、どこまでの使用を許諾するのかを契約書に明確に定めておく。
また、現地販売代理店が名刺に日本企業のロゴを印刷したり、自社のロゴと日本企業のロゴとを並記したりする(ジョイントブランド)ことがあるので、契約書には商標の使用の態様まで規定しておくことが重要。
・代理店募集の広告を出したら、勝手に商標登録されてしまった。
<対応策>
現地代理店を募集する前に、中国において商標等の出願手続きを済ませておく。
中国特許出願の優先審査について
2013.02.20 10:00
中国知識産権局(SIPO)は、2012年8月1日より発明特許出願の優先審査制度を実施しており、下記(1)~(4)に関連する発明特許出願に限り、優先審査の申請が認められている。
(1) 省エネルギー環境保護、新世代通信技術、バイオテクノロジー、ハイエンド設備製造、新エネルギー、新素材、新エネルギー自動車等の技術分野にかかわる重要特許出願
(2) 低炭素技術、資源節約等、グリーン発展に寄与する技術にかかわる重要特許出願
(3) 同一の主題について先ず中国において特許出願され、その後、他の国家・地域で特許出願された特許の中国での最初の出願
(4) その他、国家または公共の利益に重大な意義があり、優先審査が必要な特許出願
・優先審査の申請が認められた場合、中国知識産権局は、優先審査の認可日より30日(勤務日)以内に第一回審査意見通知書を発行する。
・優先審査された発明特許出願の審査意見通知書への応答期限は 2ヶ月。出願人がその応答期限を延期する場合、優先審査は中止となる。
・優先審査は、当該優先審査の申請が認められた日から一年以内に結審する。
米国特許庁、最終審査ガイドラインと施行規則を発表(速報)
2013.02.15 10:36
米国特許庁は先願主義と先公表主義に係わる最終審査ガイドラインと施行規則を発表した。
それによると主な変更点は以下の点である。
1.公表とその後の第3者の発表の主題は完全に一致している必要はない
・発表者がA+B+Cを公表してから出願し、第3者がその出願前にA+B+C+Dを発表(あるいは米国出願)した場合、第3者のA+B+Cの部分は先行技術にならず、Dのみが先行技術になる
・発明者が化合物A(スピーシーズ)を公表して出願し、第3者がその出願前に上位概念を発表(あるいは米国出願)した場合は上位概念は先行技術にならない
・発明者が上位概念を公表し、第3者が化合物A(スピーシーズ)を発表(あるいは米国出願)した場合は、化合物A(スピーシーズ)は先行技術となる
・このような発明者の公表と第3者の発表(米国出願)の比較においては、発明者の出願のクレームは一切関係がない2.2013年3月16日以降の出願
・その出願は、有効出願日が3月16日以降であるクレームが1つでも、いかなるときにでもあれば新法適用となる。そのクレームが審査でキャンセルされても新法適用となる
・新法適用の出願から現行法適用のクレームのみを分割しても新法適用となる
・RCEとPCT国内移行出願はいかなるクレームでも現行法適用である(そもそも新規事項があることはありえないので)
・PCT出願を国内移行でなく、継続出願するか一部継続出願した場合は有効出願日が新しいクレームが1つであるかによって新法適用か現行法適用かが決定される
・新法適用となるクレームがある場合は、出願から4ヶ月以内(優先権主張出願の場合は元の出願から16ヶ月以内)にその旨の供述書を提出しなければならない
・そのようなクレームがないと出願人がリーゾナブルに信ずる場合は、そのような供述書を提出する必要はない
(注:原案には明細書に新規事項が追加されたが、クレームにはない場合にも供述書を提出することが義務付けられていたが、それは削除されている模様である)3.その他の点では特別の修正はみらえないようであるが、現在検討中である
出所 WHDA法律事務所「米国特許ニュース(2013年2月14日)」より
第5回 商標の登録要件(2)
2013.02.13 10:00
今回は、二つ目の登録要件について説明します。前回説明しました一つ目の登録要件を満たしている商標であっても、この二つ目の登録要件を満たしていない商標は、登録が認められません。
二つ目の登録要件には、一つ目の登録要件と同様に、様々のものが規定されていますが、今回は拒絶理由として最も頻繁に採用されているものについてご説明いたします。 それは、具体的にどういった要件かと言いますと、他人の登録商標と同一・類似範囲にある商標は登録を認めないという要件です。商標は、自社の商品またはサービスに使用するものであるため、自社の商標と他社の商標(登録商標)との同一・類似関係と、自社が商標を使用している商品・サービスと他社が登録商標を使用している商品・サービスとの同一・類似関係が問題となります。つまり、自社の「商標」及び「商品・サービス」の双方が、他社の「登録商標」及びその登録商標の「指定商品・サービス」と、同一・類似関係にある時は、その商標の登録が認められないということです。従いまして、自社の商標と他社の登録商標とが非類似の場合や、自社が商標を使用している商品・サービスと他社が登録商標を使用している商品・サービスとが非類似の場合は、他の要件を満足していることを前提として、登録が認められます。
また、商標権は、登録商標と同一・類似範囲内における他人の商標の使用を阻止することができる権利であるため、この要件を満たしていないために登録が認められない場合は、他人の商標権を侵害している可能性が高いということです。従いまして、この理由で拒絶された場合、その商標を使用し続けることは、よろしくないということになりますので、商標の変更等をご検討ください。
さらに、登録されていなくても、世の中に広く知られた商標(周知商標)や有名な商標(著名商標)と同一・類似範囲内にある商標は登録を認められません。特に、著名商標に類似する商標については、著名商標を使用している商品・サービスと非類似の商品・サービスに使用する場合であっても、混同を生じるおそれがあるときは、登録が認められませんので、ご注意願います。
弁理士 西村陽一
米国特許商標庁、2013年3月19日からの料金発表
2013.02.08 11:34
1.米国特許商標庁、2013年3月19日からの料金発表
米国特許商標庁は2013年3月19日からの新料金を発表した。
それによると主要項目の料金は添付1の表に示される通りとなるが、それらの概略は以下の通りである。・出願料金(基礎、サーチ、審査料金)・・・1,600ドル(約30%増)
・クレーム超過料金・・・30~70%増
・期間延長料金・・・10~30%増
・RCE・・・1回目は1,200ドル、約30%増で、2回目以降は1,700ドル、83%増
・審判・・・2800ドル(43%増)
・維持年金・・・平均約40%増
・査定系再審査等の各種特許無効手続・・・これらは原稿料金より約20%減額されている最終決定された新料金は昨年9月に発表された料金案よりは抑えられているが、それでも高額の米国特許出願手続きとなる。
米国特許商標庁は、審査の質や得られる特許の質を向上させ、且つ滞在を減少させるためにはやむを得ない措置であると説明している。
2.審査ガイドラインの最終版は2013年2月16日までに制定
米国特許商標庁は、審査ガイドラインやそれに関する新規則の最終版を新法の先願主義が施工される2013年3月16日の1ヶ月前の2月16日までに制定しなければならない。
しかし、2月16日は土曜日なので恐らく15日(金)か18日(月)に発表するものと予想される(勿論、その前に仕上げられれば早く発表する事はあり得るが修正の複雑さからその可能性は低い)。
特許制度には最も影響のある発言力を有する全米知財弁護士協会(AIPLA)と知財所有者協会(IPO)は、審査ガイドラインや関連規則のドラフトの下記の点について非常に強い反対意見を出しているのでこれらの点はかなり修正される事が予想される。
(1)優先権証明書や、明細書ないしクレームに新規事項があるか否かに関する供述書の提出期限(ドラフトでは出願から4ヶ月、優先権主張日から16ヶ月以内等)は不要。
(2)3月16日以降の新出願が新法適用となるような機会を与えるべき等。
(3)先行技術となる「販売」には、「販売の申し出」も入り、且つ「公けの販売」でなければならない。
(4)出願前の公表が第3者のその後の発表を排除するためには両者は同一でなければならないとするドラフトは完全な誤りで、少なくとも同じ主題(subject matter)は排除できるとすべし(この点については筆者はEli Lilly社のArmitage部長のコメントがベストと考える)。
(5)新法出願の全てのクレームをインターフェアランス利用可能とする解釈は誤り。
(6)「発明者」の明確化
(7)23の異なる出願具体例について、それぞれの推定有効出願日はいつか、新法適用となるか従来法適用となるか等について最終ガイドラインには米国特許商標庁の見解を示すべきである(AIPLA提案)。その出願例の一つは、例えば、2013年3月16日以前の外国出願は明細書A、クレームXであり、3月16日以降の優先権主張の米国出願は明細書AでクレームX’であったとする。X’のサポートが元の明細書Aにある場合(§112条を満足)と、ない場合(§112条の問題あり)のそれぞれの新出願の推定有効出願日と新法か従来法かの適用はどうなるのか。
以上のコメントにより、最終審査ガイドラインや関連規則はかなり修正される事が予想される。
出所 WHDA法律事務所「米国特許ニュース(2013年1月24日)」より
第4回 商標の登録要件(1)
2013.02.06 10:00
商標出願すれば、その商標が必ず登録されるというものではありません。では、どのような商標が登録を認められるのでしょうか。
商標の登録が認められるためには、通常、二つの登録要件を満たしている必要があります。
一つ目の登録要件は、商標の本来的な機能である自他商品識別力(または自他役務識別力)を備えている必要があるということです。つまり、他社の同種の商品やサービスから自社の商品やサービスを区別できるような力を持った商標でなければならないということです。
商標法では、こういった識別力のない商標を5つに分類して具体的に規定しています。
1.商品やサービスの普通名称(略称や俗称も含む)
Ex. 「時計」という商品について、商標「時計」
「損害保険の引き受け」というサービスについて、商標「損保」
「箸」という商品について、商標「おてもと」
2.慣用商標(商品やサービスについて慣用的に使用されている商標)
Ex. 「清酒」という商品について、商標「正宗」
「宿泊施設の提供」というサービスについて、商標「観光ホテル」
3.商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途やサービスの提供場所、質等
を表示する商標
Ex. 「菓子」という商品について、商標「阿寒湖」
4.ありふれた氏または名称
Ex. 「スキー用具」という商品について、商標「西沢スキー」
5.極めて簡単で、かつ、ありふれた商標
Ex. 「△」、「○」、「AA」、「卍」、「エーケー」、「200」、「L-IP」自社の商品の内容が即座に分かるように、商品の一般名称や機能のみからなる商標を登録したいといって来られる方がよくいらっしゃいますが、その場合は識別力のある特徴的なネーミングを付加していただくと、登録可能性が高くなります。
次回は、二つ目の登録要件について説明いたします。