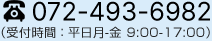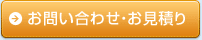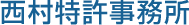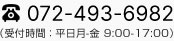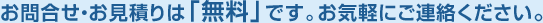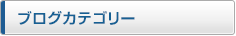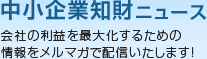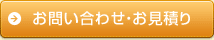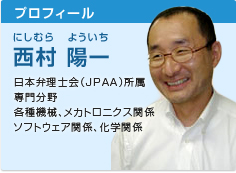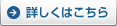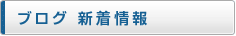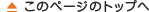カテゴリー:不正競争防止法
不正競争防止法(11)
2014.03.28 11:23
<営業秘密侵害に関する裁判例で、秘密管理性はどのように判断されているか。>
不正競争防止法2条6項の「秘密として管理されている」というためには、「当該情報の保有者に秘密に管理する意思があり、当該情報について対外的に漏出させないための客観的に認識できる程度の管理がなされている」必要があります(会計事務所顧問先名簿事件 大阪地裁平成11年9月14日判決)。
そして、「客観的に認識できる程度の管理がなされている」というためには、通常、
①当該情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であることを認識できるようにしていること
②当該情報にアクセスできる者が制限されていること
が必要である、とされます(プロスタカス顧客名簿事件 東京地裁平成12年9月28日判決)。
また、要求される情報管理の程度や態様は、秘密として管理される情報の性質、保有形態、企業の規模等に応じて決せられるものとされます(小松一雄 不正競業訴訟の実務P.333)。
そして、営業秘密に関する事案は元従業員等が関与する場合がほとんどですが、裁判所が請求を認容した事案も、元従業員等の行為が自由競争の範囲を逸脱していると思われる場合に、元雇用主を救済するために、元雇用主の有していた情報のうちどこまで秘密として管理されていた営業秘密として保護できるかということを検討し、請求の当否を判断していると思われる場合も少なくありません。
そのような事情を反映して、秘密管理性等の営業秘密の要件、不正取得等の要件が全体的に勘案されています。したがって、裁判例における営業秘密の要件の検討に当たっては、個々の要件ごとに検討するとともに、事案全体を見て、相互の要件の関係も検討する必要があると指摘されています(上掲書p.343-344)。
不正競争防止法(10)
2014.03.19 10:00
<不正競争防止法第2条第1項第3号請求主体について>
3号制定の趣旨は、費用、労力を投下して、商品を開発して市場に置いた者が、費用、労力を回収するに必要な期間の間、投下した費用の回収を容易にし、商品化への誘因を高めるために、費用、労力を投下することなく商品の形態を模倣する行為を規制するというものです。
従って、独占的販売権者が、差止請求、損害賠償請求及び信用回復措置請求の請求主体となりうるか否かについては、形態模倣の対象となる商品を自ら開発・商品化して市場に置いたものに限られるとする見解と、自己の利益を守るために形態模倣による不正競争を阻止して先行者の商品形態の独占を維持することが必要であり、商品形態の独占に強い利害関係を有する者についても含まれるとする見解とがあります。
前者の立場は、3号の規定の趣旨から、同号所定の不正競争行為につき差止ないし損害賠償請求できるものは、形態模倣の対象とされた商品を自ら開発・商品化して市場に置いたものに限られるべきというもので、単に輸入業者として流通に関与し、あるいはライセンシーとして同種商品の製造につき許可を受けた者は、開発・商品化した者ということはできないし、投下した資金。労力やリスクは、形態の開発・商品化に関してではなく、すでに開発・商品化された商品を自らが日本国内で販売するにあたっての販路の開拓・拡大のためになされたものというべきであると判示された例があります。
・キャディーバッグ事件
(東京地裁 平成11年1月28日判決 平成10年(ワ)第13395号)
不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する不正競争につき差止請求権及び損害賠償請求権を有する主体は、形態模倣の対称とされた商品を、自ら開発・商品化して市場においた者に限られるとした事例
・リズシャルメル事件
(東京地裁 平成12年7月18日判決 平成11年(ワ)第29128号)
原告は、原告の企業努力により、下着に付された本件商標は、原告の輸入販売するリズシャルメル社の商品を表す商品表示等として著名になっていると主張したが、裁判所は、その主張自体によっても、本件商標は、リズシャルメル社に由来する商品であることを示す表示として取引社・需要者の間で認識されていたのであって、原告の商品であることを示す表示として知られていたものではないと認定し、本件における原告は、単なる輸入代理店であって、不正競争防止法上の請求主体とはなり得ないと判示した事例
一方、後者の立場は、独占的販売権を認められた者は、結果として、当該地域における当該開発商品の市場利益を独占できる地位を得ることになりますが、独占的販売権者が有するこのような独占的地位ないし利益は、後行者が模倣行為を行うことによって、その円満な教授を妨げられる性質を有するものであるとの前提で、この独占的地位ないし利益は、上記のような同号が保護しようとした開発者の独占的地位に基礎を有し、いわばその一部が分与されたものということができるから、第三者との関係でも法的に保護されるべきとするものです。
独占的販売権者は、独占権を得るために、開発者に対し、当該開発商品を流通段階で取り扱う単なる販売権者に課されない相応の負担(最低購入量の定めなど)を負っているのが通常で、開発者は商品化のための資金、労力及びリスクを、商品の独占の対価の形で回収し、独占的販売権者はそれらの一部を肩代わりしていることになりますから、独占的販売権者を保護の主体として、これに独占を維持させることは、商品化するための資金、労力を投下した成果を保護するという点でも、同号の立法趣旨に適合します。
・ヌーブラ事件
(大阪地裁 平成16年9月13日判決 平成15年(ワ)第8501号)
先行者から独占的な販売権を与えられている者(独占的販売権者)のように、自己の利益を守るために、模倣による不正競争を阻止して先行者の商品形態の独占を維持することが必要であり、商品形態の独占について強い利害関係を有する者も、第3号による保護の主体となりうるとした上で、独占的販売権者の請求は認められるとした事例
次に、共同開発者の一方が、第三者と組んで販売する行為は差止等の請求主体になり得るか否かが問題となりますが、共同開発者甲、乙それぞれが、当該商品を商品化して市場に置くために、費用や労力を分担した場合には、第三者の模倣行為に対しては、両者とも保護を受けることができる立場にあることはいうまでもありません。しかし、甲、乙間においては、当該商品が相互に「他人の商品」に当たらないため、当該商品を販売等する行為を不正競争行為ということはできません。そこで、どの程度の関与をすれば共同開発者といえるか、つまり商品化について費用や労力をいかに投下したかについては、個別の事案検討がされるものと思われます。
・携帯液晶ゲーム事件
(東京地裁 平成12年7月12日判決 平成10年(ワ)第13353号)
甲、乙それぞれが、当該商品を商品化して市場に置くために、費用や労力を分担した場合には、第三者の模倣行為に対しては、両者とも保護を受けることができる。甲、乙間においては、当該商品が相互に「他人の商品」に該当しないとし、商品の共同開発者の一人が、他の共同開発者の許諾なく該商品を販売しても不正競争行為ということはできないと判事した事例
・シチズン時計事件
(東京地裁 平成11年6月29日判決 平成9年(ワ)第27096号)
原告シチズン商事が新規腕時計商品の企画を提案し、これに基づいて原告シチズン時計が腕時計の具体的な形態仕様を捜索していると認められ、原告ら両名が共同して原告ら商品の形態を開発したといえるし、販売業者であったとしても、共同して商品の形態を開発した場合には、差し止め、損害賠償請求は求められるとした事例
・シチズン時計事件
(東京地裁 平成11年6月29日判決 平成9年(ワ)第27096号)
原告シチズン商事が新規腕時計商品の企画を提案し、これに基づいて原告シチズン時計が腕時計の具体的な形態仕様を捜索していると認められ、原告ら両名が共同して原告ら商品の形態を開発したといえるし、販売業者であったとしても、共同して商品の形態を開発した場合には、差し止め、損害賠償請求は求められるとした事例
不正競争防止法(9)
2014.03.12 10:00
<不正競争防止法第2条第1項第3号の適用除外における「日本国内において最初販売された日から起算して3年」について>
・不正競争防止法 第19条第1項
第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
第5号イ
日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
1.保護期間の始期
現行法では、保護期間を「日本国内において最初販売された日から起算して3年」と規定しており、保護の終期の起算点のみを記載し、保護期間の始期が明確に規定されていないことから「最初に販売された日」とはいつかが問題となります。
この点については、未だ現に販売していない以上、「営業上の利益」の存在が明らかではないので、不正競争防止法による保護を一律に認めるのは困難であるとする一方で、個別の事案によっては、発売前であっても発売に向けて客観的に十分な準備を進めていたような場合には、営業上の利益の侵害が認められるとして訴訟上の保護を与えるのが妥当とする見解がありますが、「最初に販売された日」とは、商品の形態が確認できる状態での販売のための広告活動や営業活動を開始した日」(経済産業省知的財産制作室編集『逐条解説不正競争防止法』(平成21年改正版)(有斐閣、2010年)とする説が有力です。
・ハートカップ事件
(神戸地裁 平成6年12月8日判決 平成6年(ヨ)第487号)
(名古屋地裁 平成9年6月20日判決 平成7年(ワ)第1295号)
「最初に販売された日」とは、商品の形態が確認できる状態での販売のための広告活動や営業活動を開始した日であると判示(神戸地裁)
「最初に販売された日」とは、商品を初めて市場に出荷した時点と判示。本件では、サンプル出荷の日とされた。
2.改良品について「最初に販売された日」
先行開発者が投下した費用、労力を回収することが3号の趣旨であることから、改良品は先行品に対して、新たな投下費用・労力が回収を要する程度でなければならないと解されています。従って、改良品と先行品を比較して両品の形態が実質的に同一である場合には、先行品が最初に販売された日をもって、「日本国内において最初に販売された」日であると解されています。
・建物空調ユニットシステム事件
(東京高裁 平成12年2月17日判決 平成11年(ネ)第3424号)
「最初に販売された日」の対象となる「他人の商品」とは、保護を求める商品形態を具備した最初の商品を意味するのであって、このような商品形態を具備しつつ、若干の変更を加えた後続商品を意味するものではないと判断された。
・自動排泄処理装置事件
(東京地裁 平成23年2月25日判決 平成20年(ワ)第26698号)
改良品を先行品と対比したうえで、原告が、改良品の商品形態として、その模倣について不正競争防止法2条1項3号による保護を求め得るのは、改良品の形態のうち、先行品の形態と実質的に異なる部分に基礎を置くものでなければならないとすべきと判事。
3.発売前に模倣品が出回った場合の「最初に販売された日」
平成17年報告書(産業構造審議会知的財産政策部会 不正競争防止法小委員会 「不正競争防止法の見直しの方向性について」)は、「現行規定では、保護の終期の起算点のみを記載するが、発売前の模倣品から保護されるか否かなど、保護期間の開始時期は明確には規定されていない。(中略)個別の事案によっては、発売前であっても、発売に向けて客観的に十分な準備を進めていたような場合には、営業上の利益の侵害がみとめられるとして訴訟上の保護を与えることは当然である」としています。
なお、他人の模倣があったとしても、自ら商品化し、市場に流通しない場合は「他人の商品」とはいえないため、保護を求めることはできません。従って、請求できるのは発売後ですが、損害賠償は侵害行為時に遡って認められます。
・写真立て事件
(大阪地裁 平成14年2月26日判決 平成11年(ワ)第12866号)
被告製品は、原告製品よりも先に販売されていたが、このような販売時期の先後は、イ号製品…が原告製品一の模倣であり、ロ号製品…が原告製品二の模倣であるという認定を妨げるものではないと解されるし、原告製品の販売開始前に販売された被告製品の販売数量も、不正競争防止法に基づく損害賠償の算定の基礎となし得るものと判示した。
不正競争防止法(8)
2014.03.05 10:00
<不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する「模倣」とは>
・不正競争防止法 第2条第1項第3号
他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
1.同法2条5項には、「模倣」を、「他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう」と定義しています。
2.「依拠」について
「依拠」については、原告被告間の製品の形態の同一性、発売日との関係、さらには原告と被告の取引関係の有無などを考慮して判断されています。また、原告商品がマスコミ等で多数取り上げられてヒット商品となった後に被告商品が発売されているような場合には、「依拠」していると認められる可能性が高くなります。
・たまごっち事件
(東京地裁 平成10年2月25日判決 平成9年(ワ)第8416号)
・レース付き衣服形態模倣事件
(東京地裁 平成19年7月17日判決 平成18年(ワ)第3772号)
3.「実質的に同一の形態」について
本号は、基本的には商品形態のデッドコピーを規制するための規定であり、類似の形態までは規制することができません。
・ドラゴンキーホルダー事件
(東京高裁 平成10年2月26日判決 平成8年(ネ)第6162号)
作り出された商品の形態が既に存在する他人の商品の形態と相違するところがあっても、その相違が僅かな改変に基づくものであって、酷似しているものと評価できるような場合には、実質的に同一の形態であるというべきであるが、当該改変の着想の難易、改変の内容・程度、改変による形態的効果等を総合的に判断して、当該改変によって相応の形態上の特徴がもたらされ、既に存在する他人の商品の形態と酷似しているものと評価できないような場合には、実質的に同一の形態とはいえないと判示した事例
・便座シート事件
(大阪地裁 平成20年7月17日判決 平成20年(ワ)第1637号)
需要者は、原告商品の購入を検討するに際し、内側切り目を意識し、その効用を予想するものと考えられ、原告製品における内側切り目は、商品購入の際の重要な考慮要素となるものと認められることから、被告製品には、原告製品の形態上の顕著な特徴である内側切り目が全く設けられていないから、その他の原告製品の形態上の共通点を考慮しても、原告製品と被告製品とが、実質的に同一の形態であると認めることはできないと判示した事例
不正競争防止法(7)
2014.02.26 10:00
<不正競争防止法の保護対象である「商品の形態」とは >
・不正競争防止法 第2条第1項第3号
他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
1.「商品の形態」については、同法2条4項に「需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう」と定義しています。
したがって、「商品の形態」には、外観及び外部の形状に限らず、需要者において観察、確認できる内部構造も含まれる。また、商品の形状に加えて、これと結合した模様、色彩光沢及び質感が含まれます。
なお、商品の形態を離れたアイデアそれ自体については、本号の「商品の形態」にあたらないと解されています。
・宅配鮨事件
(東京地裁 平成13年9月6日判決 平成12年(ワ)第17401号)
容器の形状やこれに詰められた複数の鮨の組み合わせ・配置に、従来の宅配鮨に見られないような独自の特徴が存するような場合(例えば、奇抜な形状の容器を用いた場合、特定の文字や図柄など何らかの特徴的な模様を描くように複数の鮨を配置した場合)は、不正競争防止法の保護対象である「商品の形態」となり得ると判断した事例
・小型ショルダーバッグ事件
(東京高裁 平成13年9月26日判決 平成13年(ネ)第1073号)
実質的な小型ショルダーバッグにおいては、需要者は、その内部構造も観察、確認するなどした上で購入するかどうかを決定するのが通常であると考えられる」として、商品の外観だけでなく、需要者に容易に認識しうる商品の内部構造まで「商品の形態」に含めて認定した事例
・ドレンホース事件
(大阪地裁 平成8年11月28日判決 平成6年(ワ)第12186号)
商品の機能、性能を実現するための構造は、それが外観に顕れる場合は「商品の形態」になり得るが、外観に顕れない内部構造にとどまる限りは「商品の形態」に当たらないとした事例
2.本号では、商品形態模倣行為における商品形態について、「当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く」と規定しています。機能確保に不可欠な形態につては、これを採用しなければ商品として成立しえず市場参入できないものであるため、これを特定の者に独占させることは不適切であり、また技術的思想の保護にもつながるため、適用除外としています。
・ピアス孔保護具事件
(東京地裁 平成9年3月7日判決 平成6年(ワ)第22885号)
たとえ他人の商品が、極めて斬新で、機能及び効用が同一の商品も類似の商品も見いだせない場合においても、その商品の形態がその機能及び効用を奏するためには不可避的に採用しなければならない形態である場合、その形態は同種商品が通常有する形態に該当するとした事例
不正競争防止法(6)
2014.02.19 10:00
<不正競争防止法の「周知」及び「著名」とは >
1.他人の商品等表示が不正競争防止法第2条第1項第1号で保護されるためには、かかる商品等表示が「需要者の間に広く知られている(「周知」である)」ことが要件とされ、第2号では「著名」であることが要件とされています。
これは、本規定が商標登録を要件としないにもかかわらず、本規定により不正競争行為と判断された他人の商品等表示の使用についてはその差止や損害賠償請求が認められることから、その商品等表示が周知又は著名となっていてはじめて保護すべき法益があると考えられているからです。2.他人の商品等表示が周知であるかどうかは、商品・役務の性質・種類、取引形態、需要者層、宣伝活動、表示の内容等の諸般の事情から総合的に判断されます(逐条解説 不正競争防止法(平成21年改正版) 52頁 有斐閣)。
また、原則として、一地方で周知であれば第2条第1項第1号による保護を受けることが可能であると解されています。
・勝烈庵事件
(横浜地裁 昭和58年12月9日判決 昭和56年(ワ)第2100号)
しかしながら、問題となっている商品等表示がインターネットのオークションサイトで使用されていた場合は、かかる商品等表示が全国的に知られていることを求めた判決もあります。
・genki21事件
(東京地裁 平成22年4月23日判決 本訴:平成21年(ワ)第16809号
反訴:平成21年(ワ)第33956号)3.一方、第2条第1項第2号では、他人の商品等表示が「著名」であることが求められています。これは、そもそも本号が、競業関係の有無を問わず、著名な商品表示等の「フリーライド(ただ乗り)」、「ダイリューション(希釈化)」、「ポリューション(汚染)」を防ぐことを目的としてもうけられた条項だからです。
4.ある商品等表示が著名であるといえるためには、全国的に知られている必要があります。これは、著名な商品等表示の保護が広義の混同さえ認められない全く無関係な分野にまで及ぶものであることから、通常の経済活動において、相当の注意を払うことによりその表示の使用を避けることができる程度にその表示が知られていることが必要だと考えられるからです。
一方、ある商品等表示が著名であれば、他人が当該商品等表示を冒用することにより混同が生じるおそれがあるか否かは要件とされていません。これは、著名な商品等表示は高い経済的価値を有しており、これが侵害された場合は当該商品等表示の所有者に多大の被害が発生するため、混同の有無にかかわらず保護すべきと考えられるからです不正競争防止法(5)
2014.02.12 10:00
<不正競争防止法の「混同惹起行為」とは >
1.「混同惹起行為」には、周知の他人の商品表示又は営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と他人とを同一の商品主体又は営業主体と誤信させる、いわゆる「狭義の混同惹起行為」だけでなく、緊密な営業上の関係や同一の商品化事業を営むグループに属する関係(親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係)があると誤信させる、いわゆる「広義の混同惹起行為」も含むものと解されています。
・日本ウーマンパワー事件
(最高裁 昭和58年10月7日判決 昭和57年(オ)第658号)
・フットボール事件
(最高裁 昭和59年5月29日判決 昭和56年(オ)第1166号)
・スナックシャネル事件
(最高裁 平成10年9月10日判決 平成7年(オ)第637号)
2.また、混同が実際に生じていなくても、混同が生じるおそれがあれば「混同惹起行為」に該当します。ただし、実際の裁判では、「混同が生じるおそれがある」との心証を裁判官に抱かせる程度に立証する必要があります。例えば、以下の事項が「混同のおそれ」の判断要素としてあげられます(実務相談 不正競争防止法(初版第1刷) 172頁 商事法務研究会)
・表示の著名性や識別力の程度
・周知表示と模倣した表示の類似の程度
・商品・営業の類似、顧客層の重なりなどの競合関係
・現実の混同の発生の有無
・模倣者の悪意の存否
3.また、混同を生じるかどうかについては、「混同惹起行為」が周知表示を有する他人の営業上の利益を害するだけでなく、取引秩序の混乱につながることから、「混同惹起行為」を禁止する趣旨は公正な競業秩序の形成維持にあるとして、一般取引者及び需要者の心理を基準とし、日常一般に払われる注意力をもって判断すべきであるとされています。
・オービックス事件
(知財高裁 平成19年11月28日判決 平成19年(ネ)第10055号)
不正競争防止法(4)
2014.02.05 10:00
<不正競争防止法の「営業を表示するもの」とは >
1.不正競争防止法第2条第1項第1号は、他人の商品等表示として、「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。」と規定し、「営業を表示するもの」を保護対象としており、この「営業を表示するもの」には、例えば、営業名や図形の営業標等が含まれるといわれています。
2.これに対して、例えば、「商品陳列デザイン」は、通常、売場全体の視覚的イメージの一要素として認識記憶されるにとどまるから、それのみで営業表示性を取得するに至るとは考え難いとされています。そして、「商品陳列デザイン」だけで営業表示性を取得するような場合があるとするならば、それは商品陳列デザインそのものが、本来的な営業表示である看板やサインマークと同様、それだけでも売場の他の視覚的要素から切り離されて認識記憶されるような極めて特徴的なものであることが少なくとも必要である、とされています。
・商品陳列デザイン事件(西松屋対イオン)
(大阪地裁平成22年12月16日判決 平成21年(ワ)第6755号)
3.また、不正競争防止法上の「営業」は、経済上の収支計算に基づいて行われる活動をいい、営利を目的とするか否かを問わないとされています。例えば、「華道家元の活動」は、文化・芸術活動というべき側面を有する一方で、経済上の収支計算に基づいて行われている事業活動でもあるから、同法同号の「営業」に該当する、とされ、これらの活動に用いる「華道専正」、「華道池坊」及び「ロイヤルフラワーアレンジメント」などの名称は、事業活動のうち、華道の教授、普及その他の活動を表示するものであるから、不正競争防止法1項1号、2号の「営業等表示」である、とされています。
・華道専正池坊家元事件(西松屋対イオン)
(大阪地裁平成16年9月20日判決 平成17年(ネ)第3088号)
また、病院経営についても、「営業」に該当するとされています。
・京橋病院対京橋中央病院事件(西松屋対イオン)
(東京地裁昭和37年11月28日判決 昭和37年(ワ)第462号)
これに対して、宗教法人の宗教活動は、営業の自由の保障の下で自由競争が行われる取引社会を前提とするものではなく、不正競争防止法の対象とする競争秩序の維持を観念することができないものであるから、取引社会における事業活動と評価することはできず、「営業」に該当しないとされています。
・天理教事件
(最高裁第二小平成18年1月20日判決 平成17年(受)第575号、
東京高裁平成16年(ネ)第2393号)
不正競争防止法(3)
2014.01.29 10:00
<「商品の形態」の商品等表示性 >
1.不正競争防止法には、「商品等表示」が例示列挙されていますが、「商品の形態」は明示されておりません。 また、「商品の形態」は、通常、機能を発揮させ又は美観を高めるなどの目的で選択されるものであり、商品の出所表示を目的とするものではありません。 そこで、「商品の形態」自体が、不正競争防止法第2条第1項第1号の「商品等表示」に該当するか否かの問題が生じます。
2.「商品の形態」の商品等表示性は、判例上、以下のように扱われています。 1) 「商品の形態」が、例えば、「商品の形態が他の商品と識別し得る独特の特徴を有し、かつ、商品の形態が、長期間継続的かつ独占的に使用されるか、又は、短期間であっても商品の形態について強力な宣伝広告等により大量に販売されて使用されたような場合には、商品等表示性が肯定されています。 ・懐中電灯『マグライト』事件 (大阪地裁平成14年12月19日判決 平成13年(ワ)第10905号)
2) ただし、「商品の形態」が、「商品の製造過程及び機能的効果に必然的に結びついた形態であり、その商品の種類を示す特徴といえることができる」場合であり、この商品を「不正競争防止法第1条第1項第1号の規定で保護する」ことにより、この商品を「製造販売等する第三者の営業行為のすべてを禁圧することにつながり、同法条が本来的な商品表示として定める『他人の氏名、商号、商標、商品の容器・包装』のように、商品そのものでない別の媒体に出所表示機能を委ねる場合とは異なり、同法条が目的とする出所の混同を排除することを超えて、商品そのものの独占的、排他的支配を招来し、自由競争のもたらす公衆の利益を阻害するおそれが大きい」場合には、公正な競争維持の観点から、商品等表示性が否定されています。 ・泥砂防止用マット(コイル状マット)事件 (東京高裁平成6年3月23日判決 平成3年(ネ)第4363号) また、商品等表示性が否定された異なる例としては、競争に不可欠な商品形態、即ち、同種の商品に共通してその特有の機能及び効用を発揮するために不可避的に採用せざるを得ない形態の保護を除外する考え方があります。 ・ルーブキュービック事件 (東京高裁平成13年12月19日判決 平成12年(ネ)第6042号)
3) また、いったん獲得された商品の出所表示性であっても、その後長年の間類似形態の商品が市場に出回ることによって消滅する場合がある、とされています。 ・ギブソンエレクトリックギター事件 (東京高裁平成12年2月24日判決 平成10年(ネ)第2942号)
不正競争防止法(2)
2014.01.22 10:00
<不正競争防止法における「商品等表示」>
不正競争防止法には、「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器、商品の包装」が、「商品等表示」として条文に例示列挙されていますが、過去の判決においては、「タイプフェイス」、「マンション名」、「ウエットスーツの三色ライン」、「幼児用玩具の形態」等についても「商品等表示」と認められています。
1.タイプフェイス
「無体物であっても、その経済的価値が社会的に承認され、独立して取引の対象とされている場合には、「商品」に該当しないとするのは相当でない。」
東京高裁平成5年12月24日 平成5年(ラ)第594号)
2.マンション名
「マンションは、商取引の目的となって市場における流通が予定され、それ自体に表示を使用してその出所が識別される性質を備えている物として、不正競争防止法第2条第1項第1号にいう「商品」に該当する物とされる。」
東京地裁平成16年7月2日 平成15年(ワ)第2743号)
3.ウエットスーツの三色ライン
「…このように商品と特定の色彩・配色との組み合わせも又、商品の形態と同様、不正競争防止法一条一項一号にいう「他人ノ商品タルコトヲ示ス表示」たり得るものとはいわなければならない。」
大阪地裁昭和58年12月23日 昭和56年(ワ)第7770号)
4.「商品表示等表示性」についての主な事件の一覧
・「仮面ライダー」・「仮面ライダーV3」の姿をした人形の形態
「商品等表示」と認められなかった (昭和49年(ワ)第2092号)
・幼児用玩具の形態
「商品等表示」と認められた (平成6年(ワ)第24055号)
・システム什器の形態
「商品等表示」と認められなかった (平成12年(ワ)第12675号)
・家電の色
「商品等表示」と認められなかった (平成6年(ネ)第1518号)
・色番号
「商品等表示」と認められなかった (平成15年(ワ)第825号)
・映画の題名
「商品等表示」と認められなかった (平成17年(ネ)第10013号)