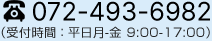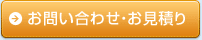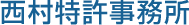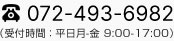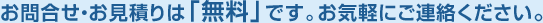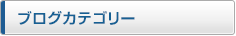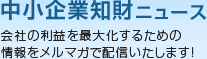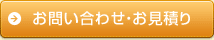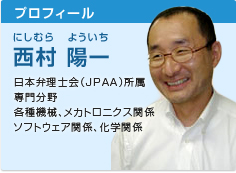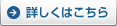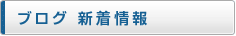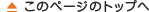カテゴリー:知的財産契約
知的財産契約(7)
2013.11.20 10:00
今回からは、共同研究開発契約について説明します。
まず、共同研究開発とは、複数の当事者がそれぞれ研究または開発の一定の分野を分担して研究・開発を行うことをいいます。
共同研究開発においては、研究成果が得られるか否かが確定しておらず、失敗に終わる可能性もありますが、失敗に終わった場合であっても、一定の財産的価値が発生する場合があります。従って、共同研究開発においては、契約の対象が曖昧であるという特徴があります。
そして、共同研究開発契約では、1)費用負担や研究・開発の分担割合といった成果を創出するための両当事者の義務遂行に関する合意事項と、2)研究開発の成果の帰属や利用等の成果の取り扱いに関する合意事項とがあり、後者の合意が最も難航するところです。
また、1)研究開発の共同化によって市場における競争が実質的に制限される場合や、2)研究開発を共同して行うことには問題がない場合であっても、共同研究開発の実施に伴う取決めによって、参加者の事業活動を不当に拘束し、共同研究開発の成果である技術の市場やその技術を利用した製品の市場における公正な競争を阻害するおそれのある場合は、独占禁止法上の問題となりますので、注意を要します。
詳しくは、公正取引委員会が平成5年4月20日に公表し、平成17年6月29日及び平成22年1月1日に改定された「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」をお読みいただくことをお勧めいたします。
○指針の構成
1)研究開発の共同化に対する独占禁止法の適用
判断に当たって考慮される事項としては、①参加者の数、市場シェア等、②研究も性格、③共同化の必要性、④対象範囲、期間等があり、①については、一般的に参加者の市場シェアが高く、技術開発能力等の事業能力において優れた事業者が参加者に多いほど独禁法上問題となる可能性が高くなります。
2)共同研究開発の実施に伴う取り決めに対する独占禁止法の適用
指針では、①共同研究開発の実施に関する事項、②共同研究開発の成果である技術に 関する事項、③共同研究開発の成果である技術を利用した製品に関する事項に区分し、それぞれについて、白色条項、灰色条項、黒色条項に分けて明らかにしています。知的財産契約(6)
2013.11.13 10:00
今回は、ライセンス契約と独占禁止法とのについて説明します。
ライセンス契約を結ぶ場合、その契約内容は、民法における契約自由の原則に基づいていかなるように定めてもよいのが基本ですが、市場における競争秩序に悪影響を及ぼす契約内容は、独占禁止法により違法として取り締まられることになります。従いまして、独占禁止法が禁止している「私的独占」、「不当な取引制限」及び「不公正な取引方法」に該当しないような内容にしておく必要があります。
独禁法21条は、「著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為については適用しない」と規定していますが、如何なる行為が独禁法上の「私的独占」、「不当な取引制限」、「不公正な取引方法」に該当するのかは一義的に確定することができませんので、公正取引委員会が平成19年9月28日に公表し、平成22年1月1日に改定された「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」をお読みいただくことをお勧めいたします。
この指針は、知的財産のうち技術に関するものを対象とし、技術の利用に係る制限行為に対する独占禁止法の適用に関する考え方を包括的に明らかにしたものですので、特許等の技術的な知的財産権に関するライセンス契約を結ぶ際に有用であると考えます。
この指針では、以下に示すように、私的独占及び不当な取引制限の観点からの考え方と、不公正な取引方法の観点からの考え方が示されており、技術の利用に関し制限を課す行為及びその他の制限を課す行為についてある程度具体的に示されています。
A.私的独占及び不当な取引制限の観点からの考え方
1.私的独占の観点からの検討
(1)技術を利用させないようにする行為
(2)技術の利用できる範囲を制限する行為
(3)技術の利用に条件を付す行為
2.不当な取引制限の観点からの検討
(1)パテントプール
(2)マルティプルライセンス
(3)クロスライセンス
B.不公正な取引方法の観点からの考え方
1.基本的な考え方
2.技術を利用させないようにする行為
3.技術の利用範囲を制限する行為
(1)権利の一部の許諾
ア 区分許諾(白色条項)
イ 技術の利用期間の制限(白色条項)
ウ 技術の利用分野の制限(白色条項)
(2)製造に係る制限
ア 製造できる地域の制限(白色条項)
イ 製造数量の制限又は製造における技術の使用回数の制限(白色条項)
(3)輸出に係る制限(白色条項)
(4)サブライセンス(白色条項)
4.技術の利用に関し制限を課す行為
(1)原材料・部品に係る制限(灰色条項)
(2)販売に係る制限(灰色条項)
(3)販売価格・再販売価格の制限(黒色条項)
(4)競争品の製造・販売又は競争者との取引の制限(灰色条項)
(5)最善実施努力義務(白色条項)
(6)ノウハウの秘密保持義務(白色条項)
(7)不争義務(灰色条項)
5.その他の制限を課す行為
(1)一方的解除条件(灰色条項)
(2)技術の利用を無関係なライセンス料の設定(灰色条項)
(3)権利消滅後の制限(灰色条項)
(4)一括ライセンス(灰色条項)
(5)技術への機能追加(灰色条項)
(6)非係争義務(灰色条項)
(7)研究開発活動の制限(黒色条項)
(8)改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務(黒色条項)
(9)改良技術の非独占的ライセンス義務(白色条項)
(10)知徳知識、経験の報告義務※黒色条項:原則として不公正な取引方法に該当する制限行為
※灰色条項:公正競争阻害性があれば不公正な取引方法に該当する制限行為
※白色条項:原則として不公正な取引方法に該当しない制限行為知的財産契約(5)
2013.11.06 10:00
今回は、ライセンス契約において、「技術的効果が認められない場合(技術面での瑕疵)」や権利に瑕疵がある場合(権利面での瑕疵)」について説明します。
1.技術面での瑕疵
例えば、特許ライセンス契約においては、「特許明細書に記載の技術的効果が認められなかった場合」や「工業的又は商業的な実施(事業化)が可能でないことが判明した場合」についても検討し、契約書に盛り込む必要があります。特許明細書に記載の技術的効果が認められなかった場合は、担保責任として、瑕疵修補請求、損害賠償請求、実施料の減額請求が可能であり、目的府達成の場合には契約解除も可能です。
具体的には、以下のような規定を設けることになります。第○条 甲(ライセンサー)は、乙(ライセンシー)に対し、本件特許発明に関し、当業者が実施した場合に本件特許権の明細書に記載された技術的効果をそうすることを保証し、工業的又は商業的実施が可能であることは保証しない。
2.権利面での瑕疵
特許無効審決の確定により実施権は消滅し、実施契約も無効となりますので、ライセンサーはそれ以降の実施料を請求することはできません。しかしながら、無効審決確定前にライセンシーが支払った実施料については、不返還特約を定めておく必要があります。
具体的には、以下のような規定を設けることになります。第○条 乙(ライセンシー)は、次の各号の一に該当する場合といえども、特許無効審決確定の日までの実施料の支払義務を免れないものとする。
(1)許諾特許に関し、特許請求の範囲が変更もしくは減縮され、または、特許を無効にすべき旨の審決もしくは取消決定が確定したとき。
(2)出願を拒絶すべき旨の査定もしくは審決が確定し、または出願が却下されたとき。また、先使用権の存在が判明した場合については、先使用権者の存在をライセンシーが予見すべきであったとはいえませんので、実施権が独占的通常実施権の場合は、以下のような規定を設けることを検討する必要があります。
第○条 本件実施権に対抗しうる先使用権が存在した場合は、乙(ライセンシー)は、先使用権の存在が明らかになった時点以降の実施料について減額を請求し、または、将来に向かって本契約を解約することができる。
知的財産契約(4)
2013.10.30 10:00
今回は、ライセンス契約において、「第三者の権利侵害によってライセンス対象の利用に障害が生じた場合」及び「ライセンス対象の利用によって第三者の権利を侵害することになった場合」について説明します。
1.権利侵害に関する担保責任
契約書上では、第三者による権利侵害に対して、ライセンサーが侵害排除義務を負う規定を設けるか否かを検討すべきであり、具体的には、以下のような規定を設けることになります。第○条 乙(ライセンシー)は本権利に関し、第三者の侵害又は侵害の恐れのある行為を発見したときは、直ちに甲(ライセンサー)に通知しなければならない。
第○条 乙(ライセンシー)は本権利に関し、第三者の本権利を侵害又は侵害する恐れのある事実を知ったときは、直ちにその旨を甲(ライセンサー)に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受けた場合には、乙と協議の上、自己の判断に基づき当該侵害行為を排除又は予防するための合理的な措置を講じるものとする。…第○条 乙(ライセンシー)は、本権利に関し、第三者による侵害の事実または侵害のおそれがある行為を発見したときは、直ちに甲(ライセンサー)に通知するものとし、必要に応じて甲乙協力してその排除または予防の措置をとるものとする。
なお、ライセンシーが専用利用権者の場合は、ライセンシーが侵害者に対する差止請求権・損害賠償請求権を有する旨の明文規定(特許法100条、102条等)が設けられていますが、通常利用権の場合はそういった規定がありません。従って、ライセンシーが通常利用権者の場合は、民法が適用されることになります。民法上、ライセンシーが通常利用権者の場合は、差し止め請求権はなく、判例は、独占的通常利用権者についてのみ損害賠償請求権を認めています。
2.第三者の権利侵害
ライセンス契約においては、ライセンシーがライセンス対象を利用することによって第三者の権利を侵害することになった場合、そのリスクをどちらの当事者が負担するのか、契約をどうするのか等を検討して契約書に盛り込む必要があります。
一般的には、以下のような規定を設けることになります。第○条 甲(ライセンサー)は、乙(ライセンシー)に対し、当該権利に係る対象の利用が第三者の本権利を侵害又は侵害しないことを保証しない。
2 本件対象の利用が前項の第三者の権利を侵害することとなる場合、本契約は当然に終了し、権利侵害が確定した時点以降の利用料の支払義務は発生しないものとする。なお、乙は、当該時点までに発生した実施料について、その支払を拒絶し、又は、甲に対し返還請求を行うことはできないものとする。知的財産契約(3)
2013.10.09 10:00
今回は、ライセンス契約におけるライセンスの対象と対価について説明します。
1.ライセンス契約の対象
まず、ライセンスの前提となる権利を特定する必要があります。
知的財産権は無体物であり、権利内容が不明確であるという特性を有していますので、その点を考慮してできるだけ明確になるように特定する必要があります。
最も確実な権利の特定方法としては、特許番号や登録番号で特定する方法です。
それ以外に、「~製品に使用されている全ての特許」といった特定方法も可能です。
なお、現在は、出願中の発明についても、仮通常実施権として予め実施許諾することが認められていますので、必要な技術については、権利発生前であっても仮通常実施権の許諾を求めることを検討することも重要です。
そして、当該特許発明又は登録商標を、実施又は使用する地域、期間、態様等を特定します。2.ライセンスの対価(実施料、使用料)
ライセンスの対価をどのように決定するかは、ライセンス契約の確信をなす要素であり、実務上も、交渉の中心をなす事項であるといえます。実施料や使用料等を、自社に如何に有利に取り決めるかが極めて重要になります。
実施料・使用料の種類としては、
①イニシャルペイメント
②ランニングロイヤリティ
③ミニマムロイヤリティ
があります。
「イニシャルペイメント」は、頭金であり、契約締結までのコストはここで回収します。
「ランニングロイヤリティ」は、売上や数量に応じて、契約期間中、継続して支払うものであり、対象製品を明確にしておく必要があります。売上に応じて支払う場合は、売上高に対して実施料率を設定し、それらを掛け合わせた値をロイヤリティとするのが一般的です。
「ミニマムロイヤリティ」は、売上等に関係なく最低限支払うランニングロイヤリティです。ランニングロイヤリティの収益はライセンシーの販売能力によることろが大きいので、「独占的通常実施権」を許諾するライセンス契約では考慮しておく必要があります。また、ライセンシーが実施しないときは契約を解除できるようにしておくことも検討する必要があります。知的財産契約(2)
2013.10.02 10:00
今回は、知的財産契約の中で最も重要度の高いライセンス契約について説明します。
契約の主たる法律関係は、以下の3つです。
1.誰と誰が合意したのか
2.何についての合意したのか
3.どういう債権債務を負うか
従って、契約書においては、まず、「当事者」、「契約対象」及び「債権債務の内容」を特定する必要があります。知的財産に関するライセンス契約とは、特許権者や商標権者が当該特許発明の実施や当該登録商標の使用を他人に認める実施権を設定する契約であり、ライセンサー(特許権者や商標権者等)は、ライセンシー(他人)による特許発明の実施や登録商標の使用に対して法的措置をとらないという義務を、ライセンシーはこれに対して対価の支払い義務をそれぞれ負うことになります。
実施権としては、設定の範囲内で特許発明(登録商標)等を独占的に実施(使用)できる専用実施権(専用使用権)と、設定の範囲内で特許発明(登録商標)等を単に実施(使用)できる通常実施権(通常使用権)とがあり、特許権者や商標権者は、同一の発明(商標)について複数の専用実施権(専用使用権)を異なる他人に重複して設定することはできませんが、同一の発明(商標)について複数の通常実施権(通常使用権)を異なる他人に重複して設定することができます。
前回説明しました知的財産権の特性を考慮しますと、知的財産に関するライセンス契約のポイントは以下のようになります。
1.ライセンス契約の対象を明確にする(権利内容の不明確性)
2.ライセンスの対価はどのようにして定めるのか(経済的価値の不確実性)
3.知的財産権が侵害され、利用に障害が生じた場合にどうするのか
(権利侵害の容易性)
4.技術的効果が認められない場合や権利に瑕疵がある場合にどうするのか
(権利の脆弱性)
5.独占禁止法に規定している不公正な取引方法に該当しないようにする
(権利の事業支配力性)次回から各ポイントについて、細かく説明していきます。
知的財産契約(1)
2013.09.25 10:00
今回から知的財産に関する契約についての講座を開設します。
今回は、まず、知的財産の特殊性に着目して知的財産契約の全体像を説明いたします。
まず、知的財産契約は、大きく以下の5つに分類されます。
1.知的財産権の移転に関する契約(権利譲渡契約、職務発明契約等)
2.知的財産権の利用に関する契約(ライセンス契約等)
3.知的財産権の創出に関する契約(共同研究開発契約等)
4.知的財産権を担保化するための契約(知的財産担保契約等)
5.その他(秘密保持契約)知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を推進することを目的として制定された知的財産基本法では、「知的財産権」を、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利と定義しています。なお、「育成者権」とは、品種登録された植物の新品種を業として独占的に利用する権利のことをいいます。
こういった知的財産権には以下のような特質がありますので、これらの特質に配慮した契約条項が必要になります。
1.権利侵害の容易性
取引の対象が無体物であるため、物理的支配ができず、無権利者であっても容易に知的財産を利用することができます。
2.権利内容の不明確性
例えば、特許権の権利範囲は、特許請求の範囲により確定されますが、その内容は有体物のように明確ではなく、どの部分が取引の対象になっているかも明確ではありませ ん。
3.経済的価値の不確実性
知的財産権について交換価値を把握するのが難しく、知的財産権を利用した場合の対価を客観的に把握するもの難しいという不確実性を有しています。
4.権利の脆弱性
知的財産権は、後日無効になる可能性を有しています。
5.権利の経済財としての事業支配力性
知的財産権は、経済財として事業支配力の強力な武器となるため、社会的影響力が大きく、経済秩序との調和という視点が求められています。また、知的財産契約は、民法に規定されている「契約自由の原則」により、その内容を自由に定めることができますが、民法90条に規定されている公序良俗に反する場合や民法91条に規定されている強行規定に反する場合は、契約自体が無効となりますので、そのあたりも考慮する必要があります。
特に、ライセンス契約等において、不公正な取引方法に該当する場合は、独占禁止法からの規制も受けますので、不公正な取引方法に該当しないような契約条項を作成する必要があります。