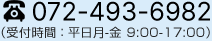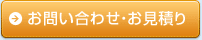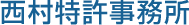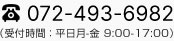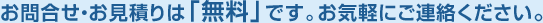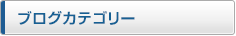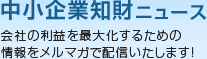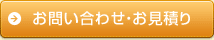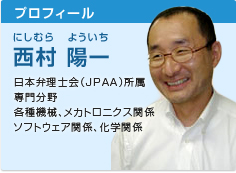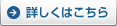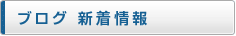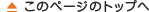カテゴリー:商標講座
第10回 商標の類否判断(4)
2013.09.11 10:00
今回は、前回に続いて結合商標の類否判断、特に、審査基準に挙げられている7つの具体例について説明します。
1)形容詞的文字(品質や原材料等を表示する文字)を有する結合商標は、それが付加されていない商標と類似する。
Ex.「スーパーライオン」と「ライオン」は類似
※「スーパー」は、商品の品質表示
※「スーパー」を別の語に置き換えることによって登録可能性が高くなる場合があります。
2)大小のある文字からなる商標は、原則として大きさの相違するそれぞれの部分からなる商標と類似する。
Ex.「富士白鳥」と「富士」または「白鳥」とは類似
※「富士」または「白鳥」という商標が既に登録されている場合は、「富士白鳥」というふうに両者の文字サイズを同じにして、できるだけ「富士」と「白鳥」とが一体不可分であるように表示することで、登録可能性が高くなります。
3)著しく離れた文字の部分からなる商標は、原則として、離れたそれぞれの部分のみからなる商標と類似する。
Ex.「鶴亀 万寿」と「鶴亀」または「万寿」とは類似
※「鶴亀」または「万寿」という商標が既に登録されている場合は、「鶴亀万寿」というふうに両者を連続して表示することで、登録可能性が高くなります。
4)長い称呼を有するため、又は結合商標の一部が特に顕著であるため、その一部分によって簡略化される可能性がある商標は、原則として、簡略化される可能性がある部分のみからなる商標と類似する。
Ex.「cherryblossomboy」と「チェリーブラッサム」とは類似
※こういった商標は、簡易迅速を旨とする取引きには必ずしも適さないため、実際の取引きにおいては、その一部が省略されてそれ以外の部分をもって略称されることが少なくないからです。
※あまり長い称呼を有する商標は、読みにくく、言いにくく、覚えにくいので、良い(売れる)ネーミングとはいえませんね。
5)指定商品又は指定役務について慣用される文字と他の文字とを結合した商標は、慣用される文字を除いた部分からなる商標と類似する。
Ex.清酒について「菊正宗」と「菊」とは類似
※「正宗」は、指定商品「清酒」についての慣用商標
※例えば、「清酒」について、「正宗」という語を使用したいのであれば、「正宗」と結合させる他の語の登録可能性を高める必要があります。
6)指定商品又は指定役務について需用者の間に広く認識された他人の登録商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その他人の登録商標と類似するものとする。
Ex.化粧品について「ラブロレアル」と「L’REAL」や「ロレアル」とは類似
※有名ブランドの登録商標を商標の一部に使用すると、商標登録が認められないばかりではなく、商標権侵害として提訴される恐れもありますので、使用しないようにしましょう。
6)商号商標については、商号の一部分として通常使用される「株式会社」「紹介」「CO.」「K.K.」「Ltd」「組合」「協同組合」等の文字が出願に係る商標の要部である文字の語尾又は語頭のいずれにあるかを問わず、原則として、これらの文字を除外して商標の類否を判断するものとする。
※「株式会社」「紹介」「CO.」「K.K.」「Ltd」「組合」「協同組合」等の文字は識別力がないため、このように取り扱うのは当然でしょう。弁理士 西村陽一
第9回 商標の類否判断(3)
2013.09.04 10:00
今回は二以上の語、図形または記号の組み合わせからなる商標(これを、「結合商標」といいます。)の類否判断について説明します。
商標の審査基準には、「結合商標の類否の判断は、その結合の強弱の程度を考慮し、例えば、次のように判断するものとする。ただし、著しく異なった外観、称呼又は観念が生ずることが明らかなときは、この限りではない。」と規定されており、具体例としては、7つのパターンが挙げられています。
商標の類否判断は、基本的に商標を構成する全体の文字等により生ずる外観、称呼または観念により行うのが原則です。しかし、結合商標については、その結合の程度が弱い場合は、分離して類否判断するということです。
二以上の語の結合の状態は、以下点を考慮して認定されます。
①構成上一体であるか
②全体の構成から一定の外観、称呼又は観念が生ずるか
③自他商品の識別力を有する部分とそうでない部分がないか
④一部に特に需用者に印象づける部分がないか
⑤称呼した場合淀みなく一連に称呼しうるかつまり、これらが否定されるときは、結合の程度が弱く、識別力を有する構成の一部(要部)をもって取引きに使用される場合が少なくないからという理由で、一部を分離ないし抽出して類否判断がなされることになります。
なお、自他商品又は役務の識別力が強くない語同士の結合の場合は結合の状態が強く、一連に称呼、観念されるのが経験則であるとする判例があります(平成14年(行ケ)266号 東京高平成15年1月21日 速報334-11278)。
次回は、審査基準に挙げられている具体例について説明します。
弁理士 西村陽一
第8回 商標の類否判断(2)
2013.08.28 10:00
第7回の「商標の類否判断(1)」では、商標の有する「外観」、「称呼」及び「観念」といった判断要素について説明しましたが、今回は、商標の類否判断を行う判断主体についての基準を説明します。
商標の審査基準には、「商標の類否の判断は、商標が使用される商品又は役務の主たる需要層(例えば、専門家、老人、子供、婦人等の違い)その他商品又は役務の取引きの実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならない。」と規定されています。
1.「取引きの実情」とは、以下に示すようなことを意味しています。
・需要者の範囲(「専門家(商品が原材料)」か「一般消費者(商品が最終製品)」か)
・商品の流通経路(例えば、商品の販売主体が専門業者か一般小売業者か)
・商標の採択の傾向(例えば、薬剤は「ドイツ語」、化粧品は「フランス語」等)
・商標の使用状態(取引きが商標より生ずる称呼によるのか、全体構成の外観によるのか)2.「需要者の通常有する注意力」
「需要者」には、取引者及び一般消費者の双方が含まれ、「取引者」とは、当該商品の製造・販売または役務の提供に従事し、一定の商品や役務の知識を有する者を言います。
そして、商標に払われる注意力は商品や需要者によって異なるので、それぞれに応じた注意力を基準にして判断するということです。
・子供は、欧文字や漢字の違いは分かりにくいが、図形やキャラクターの違いは見分けやすい
・安価な使い捨て商品と高価な耐久商品とでは注意力が異なる
・一般消費者が払う注意力と専門家が払う注意力とは異なる
・注意力が散漫な者や慎重な者は基準とならない弁理士 西村陽一
第7回 商標の類否判断(1)
2013.08.21 10:00
第5回の「商標の登録要件(2)」では、「他人の登録商標と同一・類似範囲にある商標は登録を認めない」という登録要件について説明しましたが、今回は、この登録要件に関連して、対比する二つの商標が類似か否かの判断をどのように行うかについて説明します。
商標の審査基準には、「商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない。」と規定されています。通説的な見解によれば、比較する商標の有する外観、称呼(呼び方)または観念(意味)のいずれかにおいて相紛らわしく、それぞれを同一または類似の商品または役務に使用したときに出所の混同を生じるおそれがある場合、両商標は類似であると判断するということ担っていますが、例えば、称呼は相紛らわしいが両商標の外観及び観念が相違することにより、全体として相紛らわしくない場合は、称呼の面だけからみて類似の商標と判断するのではなく、外観及び観念上をも含めて総合的に考察して、両商標の類否を判断すべきであるということです。例えは、商標A(「痛快!」)と商標B(「Tsu Kai」)とは、「ツウカイ」と「ツーカイ」という類似した称呼を生じるが、両商標は、外観において著しく相違するものであり、商標Aからは「痛快」、「とても気持ちの良いこと」、「大変愉快なこと」等の明確な観念を生じるのに対して、商標Bからは特定の観念が生じないと共に、何らかの意味合いをもって把握されることもないから、両商標は観念において明瞭に相違するとして、東京高裁は非類似として判断したという事例があります。
ただし、特許庁の審査実務では、称呼のみによって判断されることが多いので、弊所が商標の登録可能性を判断する際は、安全サイドに立って、比較する両商標の称呼が相紛らわしい場合は、両商標は類似する可能性が高いものと判断しています。
1.称呼上類似するとされた事例
・「OLTASE・オルターゼ」と「ULTASE」 東京高裁昭和60年(行ケ)第180号
・「BARICAR」と「バルカー」 東京高裁昭和60年(行ケ)第170号
・「pba」と「BBA」 東京高裁昭和60年(行ケ)第229号2.観念上類似するとされた事例
・「星(図形)」と「レッドスター」 東京高裁昭和37年(行ナ)第215号
・「FROM A TO Z」と「A to Z」 東京高裁平成9年(行ケ)第96号
・「伏見の竜馬」と「竜馬」 東京高裁平成13年(行ケ)第122号
・「ふぐの子」と「子ふぐ」 東京高裁平成14年(行ケ)第377号弁理士 西村陽一
第6回 商標の登録要件(3)
2013.04.10 10:00
前回は、二つ目の登録要件のうち、拒絶理由として最も頻繁に採用されている要件「他人の登録商標と同一・類似範囲にある商標は登録を認めない」についてご説明しましたので、今回は、その他の要件について簡単にご説明します。
以下に示す商標は登録が認められませんので、商標を採択する場合はご注意ください。
1.国旗、菊花紋章、勲章、褒章または外国の国旗と同一または類似の商標
2.パリ条約の同盟国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣が指定するものと
同一または類似の商標
3.国際連合その他の国際機関を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するも
のと同一または類似の商標
4.白字赤十字の標章、赤十字の名称、ジュネーブ十字の名称と同一または類似の商
標
5.国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって、営
利を目的としないものまたは公益に関する事業であって営利を目的としないも
のを表示する標章であって著名なものと同一または類似の商標
6.公序良俗を害するおそれがある商標
7.他人の肖像、氏名、名称、著名な雅号、芸名、筆名、これらの著名な略称を含む
商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
8.博覧会の賞と同一または類似の標章を有する商標
9.他人の周知商標と同一または類似の商標であって、同一または類似の商品に使用
するもの
→特許庁がインターネットで提供している特許電子図書館中の「日本国周知・著
名商標検索」でこれらの商標を検索することができる。
10.種苗法第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一または類
似の商標であって、その品種またはこれに類似する商品、役務について使用する
もの
11.他人の業務に係る商品役務と混同を生ずるおそれがある商標
→著名な商標を非類似の商品、役務に使用した場合等が該当する。
12.商品の品質または役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
→その品質又は質がその商品又は役務に現実に存在すると否とを問わず、その商
品が有する品質又は役務が有する質として需要者において誤認される可能性
がある場合は該当する。
13.ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示
14.商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状
15.他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標
→外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されていない
ことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り的に出願したもの、又は
外国の権利者の国内参入を阻止し若しくは代理店契約締結を強制する目的で
出願したもの等が該当する。弁理士 西村陽一
第5回 商標の登録要件(2)
2013.02.13 10:00
今回は、二つ目の登録要件について説明します。前回説明しました一つ目の登録要件を満たしている商標であっても、この二つ目の登録要件を満たしていない商標は、登録が認められません。
二つ目の登録要件には、一つ目の登録要件と同様に、様々のものが規定されていますが、今回は拒絶理由として最も頻繁に採用されているものについてご説明いたします。 それは、具体的にどういった要件かと言いますと、他人の登録商標と同一・類似範囲にある商標は登録を認めないという要件です。商標は、自社の商品またはサービスに使用するものであるため、自社の商標と他社の商標(登録商標)との同一・類似関係と、自社が商標を使用している商品・サービスと他社が登録商標を使用している商品・サービスとの同一・類似関係が問題となります。つまり、自社の「商標」及び「商品・サービス」の双方が、他社の「登録商標」及びその登録商標の「指定商品・サービス」と、同一・類似関係にある時は、その商標の登録が認められないということです。従いまして、自社の商標と他社の登録商標とが非類似の場合や、自社が商標を使用している商品・サービスと他社が登録商標を使用している商品・サービスとが非類似の場合は、他の要件を満足していることを前提として、登録が認められます。
また、商標権は、登録商標と同一・類似範囲内における他人の商標の使用を阻止することができる権利であるため、この要件を満たしていないために登録が認められない場合は、他人の商標権を侵害している可能性が高いということです。従いまして、この理由で拒絶された場合、その商標を使用し続けることは、よろしくないということになりますので、商標の変更等をご検討ください。
さらに、登録されていなくても、世の中に広く知られた商標(周知商標)や有名な商標(著名商標)と同一・類似範囲内にある商標は登録を認められません。特に、著名商標に類似する商標については、著名商標を使用している商品・サービスと非類似の商品・サービスに使用する場合であっても、混同を生じるおそれがあるときは、登録が認められませんので、ご注意願います。
弁理士 西村陽一
第4回 商標の登録要件(1)
2013.02.06 10:00
商標出願すれば、その商標が必ず登録されるというものではありません。では、どのような商標が登録を認められるのでしょうか。
商標の登録が認められるためには、通常、二つの登録要件を満たしている必要があります。
一つ目の登録要件は、商標の本来的な機能である自他商品識別力(または自他役務識別力)を備えている必要があるということです。つまり、他社の同種の商品やサービスから自社の商品やサービスを区別できるような力を持った商標でなければならないということです。
商標法では、こういった識別力のない商標を5つに分類して具体的に規定しています。
1.商品やサービスの普通名称(略称や俗称も含む)
Ex. 「時計」という商品について、商標「時計」
「損害保険の引き受け」というサービスについて、商標「損保」
「箸」という商品について、商標「おてもと」
2.慣用商標(商品やサービスについて慣用的に使用されている商標)
Ex. 「清酒」という商品について、商標「正宗」
「宿泊施設の提供」というサービスについて、商標「観光ホテル」
3.商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途やサービスの提供場所、質等
を表示する商標
Ex. 「菓子」という商品について、商標「阿寒湖」
4.ありふれた氏または名称
Ex. 「スキー用具」という商品について、商標「西沢スキー」
5.極めて簡単で、かつ、ありふれた商標
Ex. 「△」、「○」、「AA」、「卍」、「エーケー」、「200」、「L-IP」自社の商品の内容が即座に分かるように、商品の一般名称や機能のみからなる商標を登録したいといって来られる方がよくいらっしゃいますが、その場合は識別力のある特徴的なネーミングを付加していただくと、登録可能性が高くなります。
次回は、二つ目の登録要件について説明いたします。
第3回 小売役務商標について
2012.12.12 09:00
小売役務商標とは、小売業者等がその業務に係る小売・卸売に使用する商標のことをいいます。
小売業者及び卸売業者(以下、「小売業者等」といいます。)は、店舗設計や品揃え、商品展示、接客サービス、カタログを通じた商品の選択の工夫等といった、顧客に対するサービス活動を行っていますが、これらのサービス活動は、商品を販売するための付随的なサービスであること、また、対価の支払いが、販売する商品の価格に転嫁して間接的に支払われ、当該サービスに対して直接的な対価の支払いが行われていないことから、従来の商標法では、「役務」には該当しないとされていました。
そのため、従来の商標法では、小売業者等がサービス活動に使用する商標は、「役務」に係る商標としては保護されていませんでした。
ただし、小売業者等が商品について使用をする商標は、「業として商品を(中略)譲渡する者がその商品について使用をするもの」(商標法第2条第1 項第1号)にも該当しますから、小売業者等が取扱商品に商標を貼付したり、チラシに販売商品と共に商標を表示したりする場合は、その商標について自らが販売する商品の商標権を取得して、商品に係る商標としての保護を受けることは可能でした。
しかしながら、例えば、店内のショッピングカートに社標が表示してあったり、接客サービスをする店員の制帽・制服・名札に社標を付し、その制服等を着用してサービスを提供することは、商品との具体的な関連性を見いだせないことから、商品に係る商標としての商標権では保護されておらず、改正前の商標法の下では、小売業等の商標の保護には限界がありました。
また、多くの種類の商品を取り扱う小売業者等が商標登録する場合、小売業者等はその多くの取扱商品を指定して商標登録しなければなりませんが、そのためには、多数の区分に分類された商品を指定して出願しなければならず、区分の数に応じて課されている出願手数料や登録料、その後の維持費用等が大きな負担となっていました。
そこで、商標法が一部改正され、平成19年4月1日から、小売業、卸売業の方々が使用するマークを小売役務商標として保護する制度がスタートしました。
具体的には、以下に掲げるような標章について、小売役務商標として保護を受けることができます。
1. 店舗内の販売場所の案内板(各階の売り場の案内板)に付する標章
2. 店内で提供されるショッピングカート・買い物かごに付する標章
3. 陳列棚に付する標章
4. ショーケースに付する標章
5. 接客する店員の制服・制帽・名札に付する標章
6. 試着室に付する標章
7. その取扱商品や包装紙、買い物袋に付する標章
8.顧客が、手にとって実際に商品の確認を行うために店頭に展示された商品見本に付
する標章
9.会計用カウンターに設置される、商品の会計用のレジスターに付する標章
10.商品の販売のために商品の品揃え、商品説明などを行うインターネットサイト上に
表示する標章
11.小売店の店舗屋上に設置した看板に付する標章
12. 電車内の吊り広告に付する標章
13. 新聞広告に付する標章
14. 新聞の折り込みチラシに付する標章
15. 店舗内で展示、頒布する商品カタログ・価格表に付する標章
16. インターネットサイト上で取扱商品の広告を表示する際に表示する標章また、小売等役務は、その取扱商品が多種類の商品分野に及ぶ場合でも、ニース協定の国際分類によれば、第35類という一つの区分に属する役務であることから、小売業者等が自己の商標を小売等役務に係る商標として商標登録する場合には、改正前のように多数の区分に出願する必要がなく、第35類という一つの区分に出願すればよいので、取扱商品の範囲に応じて区分の数が多くなって出願手数料や登録料等の負担が大きくなるということはありません。
第2回 商標のはたらきについて
2012.12.05 09:00
商標は、自社の商品・サービスと他社の商品・サービスとを識別するはたらきを有しています。
例えば、私たちが商品を購入する場合、今まで使っていたブランドやCMでなじみのある商品を購入する傾向にあります。実際に店頭では、商品に表示されている商品名やロゴマークで自分の買いたい商品を探します。これは、同じ商標がついている商品やサービスは、同じ生産者や提供者が提供していることを示す、自他商品・役務の識別標識としての機能を商標が有しているからです。
また、同じ商標がついている商品やサービスは、同じ品質や質を有していると思ってどこでも安心して購入することができます。従って、商標は、商品やサービスの質を保証するはたらきも有しています。
そして、営業者が同じ商標を使用してよい商品やサービスを提供し続けることで、私たちは商標自体によいイメージを持つようになり、私たち需要者の信用が商標に蓄積されていきます。このようにして需要者の信用が蓄積された商標は、ブランドと呼ばれるようになり、営業者にとっての広告塔となります。
第1回 商標について
2012.11.28 09:00
商標法では、
「『商標』とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、
・業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
・業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの
をいう。」
と規定しています。
ここで、「役務」とは、有体物である商品を持たない飲食業、ホテル業、輸送業等といったサービス業が提供する「サービス」を意味しています。簡単に言いますと、商標は、商品や役務(サービス)に使用する名称、マーク等であり、商品に使用する商標を商品商標(トレードマーク)、役務(サービス)に使用する商標を役務商標(サービスマーク)といいます。
具体的には、以下のように分類されます。
・会社名、商品名、サービス名等のように文字だけからなる文字商標・ロゴマークのように図形だけからなる図形商標
・記号だけからなる記号商標
・文字と図形や記号とが結合した結合商標、
・キャラクター人形等のような立体商標
また、特許庁に登録されている商標を「登録商標」といい、独占的使用が認められています。