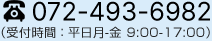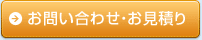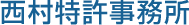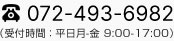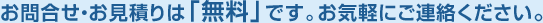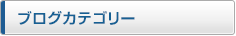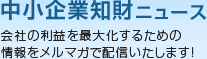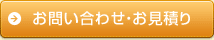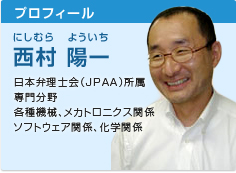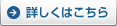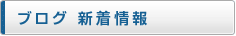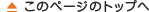カテゴリー:ネーミング
ネーミング(14)
2013.07.31 10:00
これまでネーミングについてお話してきましたが、今回で最終回となります。
商標法第3条第1項第3号(商品の品質や効能を表示しただけの記述商標)の不登録要件を回避する手法については、第6回から前回までの「ネーミングの案出手法」において、折に触れて説明してきましたが、今回は、そこでは取り上げなかったその他の3条1項3号回避に成功したネーミングの事例を列挙しておきます。9)その他の3条1項3号回避に成功したネーミングの事例
■わが家の/おいしい牛乳(牛乳)
→「おいしい牛乳」だけなら品質表示
■ホッとアイマスク(アイマスク)
→★「ホットアイマスク」なら品質表示
■ナイシトール(薬剤ほか) 効能
■養潤液(化粧品ほか) 用途・効能
■消臭力(芳香剤ほか) 用途・効能
→★「力」には「リキ」のふりがなで登録
■のどぬーる(薬剤ほか) 使用方法
■おくだけ(芳香剤) 使用方法
■メガシャキ/MEGASHAKI(加工食品ほか) 効能(目がしゃっきり)
■YOUKI食べるラー油(ラー油、調味料)
→★社名を併記して普通名称化した語を登録全14回にわたってネーミングについてお話してきましたが、いかがでしたでしょうか。
是非、これを参考にしていただき、商品やサービスが継続的に売れる「よいネーミング」を開発していただければ幸いです。
また、商品やサービスのネーミングは、ビジネス上非常に重要な役割を果たしますので、商標登録を行い、他人の模倣を阻止した状態でご使用いただければと思います。ネーミング(13)
2013.07.25 14:42
今回は、抽出・展開したキーワードから具体的なネーミング案を創出する「造語」の手法のうち、前回までお話しした7つの造語法以外のその他の様々な造語法についてお話しします。
8)その他の様々な造語法
1)回文(逆さから読んでも同じになる文)
■CIVIC(自動車)、■AVIVA(パソコン教室ほか)、■WOWOW(CSテレビ放送)
2)アナグラム(言葉の文字の並び順を入れ替えて、別の言葉にすること)
■SUNTORY(鳥井さん)、■DAKARA(身体)、■コクヨのヨコク
3)逆さ読み
■NUBRD(「ダーバン」の逆:紳士服)、■ポンテリカ(仮店舗)
4)踏韻(ある特定の専門家や仲間内だけで通じる言葉や言い回しや専門用語のこと)
■クリアクリーン、■プッチンプリン、■ファイナルファンタジー
5)掛詞
■ガンバ大阪(がんばる、gmba=イタリア語:脚力、実力)
6)語呂合わせ
■大清快(エアコン:「大正解」)、■通勤快足(靴下:「通勤快速」)
■551(豚まん:「味もサービスもここが一番」)
■GOPAN/ゴパン(家庭用パン焼き器)
7)日本語(古語)
■爽(アイスクリーム)、■紅茶花伝(紅茶飲料)、■自由区(婦人服)
8)日本語(方言)
■いいちこ(焼酎:大分方言「いいですね」)
9)擬人化
■ケイコとマナブ(雑誌)、■勘定奉行(ソフトウェア)、ミスタードーナツ(飲食業)
■ガスぬき君(エアゾールのガス抜き器具)
10)会話語
■お~いお茶(茶)、■はいれます(終身保険)、■ごはんですよ(海苔佃煮)
■キレイキレイ(薬剤ほか)
11)擬音語、擬態語、態様表現
■POCKY(菓子)、■きりり(果汁入り飲料)、■SARA(シャンプー)
■スリムドカン減肥食(食品:形容詞+擬態語+効能→3条1項3号回避)
■動くん棚、回るん棚(冷蔵庫:話し言葉+語呂合わせ→3条1項3号回避)
■らく楽○○○(らく楽ナビ、らく楽録画テレビ ほか:態様表現)
12)象徴文字
■AZ(エージー:目薬)、■XY(ゼクシィ:結婚情報誌)ネーミング(12)
2013.07.17 10:00
今回は、抽出・展開したキーワードから具体的なネーミング案を創出する「造語」の8つの手法のうち、7番目の手法「頭文字」についてお話しします。
7)頭文字(A’+B’+C’=D)
この手法は、複数の単語の頭文字を並べる、というものです。【事例】
■USJ(テーマパーク)
→Universal Studio Japan
■BMW(自動車会社)
→Bayerrisch Motren Werke AG
■DoCoMo(携帯通信事業者)
→DoCommunication over the Mobile network
■KYK(とんかつ)
→Keep You Kindly、あるいは発祥地の「瓦町洋裁研究所」の頭文字
■NAGES/ネーグス(鶏卵・果実・野菜の選別包装装置)
→Nabel Efficient Grading System
■AFLAC(保険引き受け)
→American Family Life Assurance Campany of Columbus【メリット】
・短く親しみやすい。覚えやすい。【注意点】
・著名化するまでは商品やサービスの特性が伝わらない。
・他社と混同されやすい。
・アルファベット2文字の場合は登録されにくい(3条1項6号)ネーミング(11)
2013.07.10 10:00
今回は、抽出・展開したキーワードから具体的なネーミング案を創出する「造語」の8つの手法のうち、6番目の手法「接尾語」についてお話しします。
6)接尾語(A+β→Aβ)
この手法は、一語の後ろに接尾語を付加して派生語をつくる、というものです。【事例】
■WINDOM(ウィンダム:自動車)
→win(勝つ)+dom(~の世界)
■ENERGEN
→erergy(エネルギー、活力)+gen(~を生み出す)〈3条1項3号回避〉【メリット】
・派生語を作りやすい。非類似化させやすい。普通名称や一般名称、品質表示等でも接尾語を付ければ3条1項を回避できる可能性(商標登録の可能性)がある。【注意点】
・外国語の場合、接尾語を付けることにより異なる意味になる場合がある。
例)接頭語のaster(星)→asterisk(星印)
接尾語のaster(劣悪な)→desster(災害、災厄)ネーミング(10)
2013.07.03 10:00
今回は、抽出・展開したキーワードから具体的なネーミング案を創出する「造語」の8つの手法のうち、5番目の手法「接頭語」についてお話しします。
5)接頭語(α+A→αA)
この手法は、一語の前に接頭語を付加して派生語をつくる、というものです。【事例】
■UNSNORE(アンスノール:いびき抑制薬)
→un(否定)+snore(いびきをかく) 効能そのもの!〈商標法3条1項3号回避〉
■EXGEL(エクスジェル:高機能ゴム材)
→ex(extra:範囲外の→優れた)+gel(ジェル)〈商標法3条1項3号回避〉
■BIOHAZARD(バイオハザード:コンピューターゲーム)
→bio(生命)+hazard(危機、危険)
■ASTROVISION(映像機器)
→astro(天の、宇宙の)+vision(映像)
■iMac(パソコン)
→i(知的な、インターネット対応の)+Mac
■い・ろ・は・す/ILOHAS(飲料水ほか)
→著名商標「LOHAS」を取り込みつつ、商標法4条1項11号を回避【メリット】
・派生語を作りやすい。非類似させやすい。普通名称や一般名称でも接頭語を付ければ、商標法3条1項(自他商品・役務の識別力無し)を回避できる可能性がある。【注意点】
・商標の要部とみなされない接頭語もあり、そういった接頭語を使用する場合は、それに続く語自体に識別力が要求される。
例)super、ultra、neo などネーミング(9)
2013.06.26 10:00
今回は、抽出・展開したキーワードから具体的なネーミング案を創出する「造語」の8つの手法のうち、4番目の手法「切り取り」についてお話しします。
4)切り取り(A-X→A’)
この手法は、一語から何文字か切り取る、というものです。
語頭を切り取る、語尾を切り取る、両端を切り取る等、様々な切り取り方があり、辞書に載っている略語をそのままネーミングとして用いることができる場合もあります。【事例】
■スタバ/SUTABA(コーヒーほか)
→Starbacks(スターバックス)の通称を登録
■TESTIMO(テスティモ:化粧品)
→Testimony(証拠)・・・効能の信頼性を訴求
■ドメスト(住宅用洗剤)
→Domestic(家事の)
■OPTI(オプティ:軽自動車)
→Optimum(最適な)
■アンスリー(駅構内コンビニ)
→Keihan(京阪)、Nankai(南海)、Hansin(阪神)の3つのan【メリット】
・短く親しみやすく、覚えやすい。音感が良くなる。
・自他商品・役務の識別力がない、一般名称や品質表示を商標登録可能な形にできる。【注意点】
・元のワードの意味以上に広がりを持たせることはできない。
・切り取り方によってはネガティブなワードになるおそれがある。
例)harmony(調和)→harm(害)ネーミング(8)
2013.06.19 10:00
今回は、抽出・展開したキーワードから具体的なネーミング案を創出する「造語」の8つの手法のうち、3番目の手法「ブレンド」についてお話しします。
3)ブレンド(A’+B’=C)
この手法は、二語の一部分を切り出して合成する、というものです。【事例】
■FEDEX(フェデックス:航空貨物輸送)
→FEDERAL(連邦の)+EXPRESS(急行便)〈商標法3条1項3号回避〉
■ASTALIFT(アスタリフト:化粧品)
→ASTA(明日)+LIFT(上げる)・・・掛詞「明日の美を願う、美の向上を目指す」
■ポンパレ(Webによる割引情報の提供)
→クーポン+パレード
■スキャメラ/SCAMERA(イメージスキャナ)
→スキャナー+カメラ〈商標法3条1項3号回避〉
■メタバリア(加工食品ほか)
→メタボリック(肥満)+バリア(防御)・・・効能そのもの!〈商標法3条1項3号回避〉
■ブラクローム(黒色クロムメッキ)
→ブラック(黒色)+クローム(クロム)・・・品質そのもの!〈商標法3条1項3号回避〉
■るるぶ(雑誌)
→見る+たべる+遊ぶ【メリット】
・一語としてのまとまりが良い。短く親しみやすい。
・個々の語は、自他商品・役務の識別力のない一般名称でもそれらをブレンドすることにより商標登録可能な形にできる。【注意点】
・切り出し方によっては意味が伝わりにくくなるおそれあり。ネーミング(7)
2013.06.12 10:00
今回は、抽出・展開したキーワードから具体的なネーミング案を創出する「造語」の8つの手法のうち、2番目の手法「接合」についてお話しします。
2)接合(A+B→C)
この手法は、複数の語を共通文字でつなげる、というものです。【事例】
■クルマックス(自動車保険)
→クルマ(自動車)+マックス(max最大)・・・保証の充実を訴求
■RICHAIR(リシェール:シャンプー)
→RICH(豊かな)+HAIR(髪)・・・効能、効果をイメージ〈商標法3条1項3号回避〉
■CLINICARE(クリニケア:練り歯磨き)
→CLINIC(診療所)+CARE(治療)・・・優れた効能、安心感を訴求
■BIGLOBE(ビッグローブ:インターネットプロバイダ)
→BIG(大きな)+GLOBE(地球)・・・サービスの規模・充実を訴求
■熱さまシート(氷枕ほか)
→熱さまし+シート・・・商品の機能・形状そのもの!〈商標法3条1項3号回避〉【メリット】
・ありふれた言葉を繋いだだけなのに一語としてまとまりが良く、商品特性を訴求する新しい概念を提示できる。
・造語性が高まり商標登録の可能性がより高くなる。
例えば、上述した2つ目の事例に関して、「RICH HAIR」であれば、「豊かな髪」という意味となりますので、これを商標出願しても、効能、効果を普通に表示しただけの商標(自他商品・役務の識別力無し)として登録されませんが、「RICHAIR」という造語にすることによって、商標登録の可能性が高くなります。【注意点】
・外国語の場合、接合の結果偶然にネガティブな意味を生じる場合がある。
例)dear(親愛なる)+earth(地球)→DEARTH=dearth(欠乏)ネーミング(6)
2013.06.05 10:00
今回から数回にわたって、具体的なネーミングの案出手法と代表的な事例についてお話しします。
前々回にお話ししましたネーミングの案出作業における前半のプロセスにおいて、抽出・展開したキーワードから具体的なネーミング案を創出する「造語」の作業には、これから8回にわたってお話しする8つの方法が主として用いられます。
1)組み合わせ( A + B = AB)
2つのキーワードを、基本的にそのままの形で単純に組み合わせる。【事例】
■COPPERTONE(コパトーン:日焼けオイル)
→COPPER(銅)+TONE(色合い)<3条1項3号回避>
■BANDAID(バンドエイド:絆創膏)
→BAND(帯)+AID(助け)
■POWERSHOT(パワーショット:デジタルカメラ)
→POWER(力)+SHOT(撮影)
■鼻セレブ(ティッシュペーパー)
→鼻+セレブ・・・高品質を訴求
■ライフネット生命(生命保険)
→蒸気レス+IH・・・IH方式の炊飯器で、蒸気が出ないという新機能を訴求
〈3条1項3号回避〉【メリット】
・分かり易いキーワードをそのまま繋げるので商品特性が伝わりやすい。
・片方が登録不可でも、組み合わせで一体的な造語となれば登録の可能性あり。
(「蒸気レスIH」は、「蒸気レス」「IH」では3条1項3号で拒絶のはず)
・多区分での登録可能な商標を作りやすい。【注意点】
・二語を対等関係にする必要あり。
・一方が著名商標や単なる品質表示とならないよう配慮する必要あり。
・二語が分離認識されない配慮が必要。
(スペースを入れない、文字の色・大きさ・書体を変えない等)ネーミング(5)
2013.05.29 10:00
今回は、前回に引き続き、ネーミングの案出作業を構成している 3.ネーミング(造語)作業、4.言語調査、5.商標調査、6.ネーミング案の決定についてお話します。
3.ネーミング(造語)作業
前回お話ししましたプロセスで集めたキーワードをもとに、ネーミングの案出作業を行います。キーワードがそのままの形でネームとしての要求条件を満たし、商標登録も可能な場合もまれにはありますが、現実には、抽出あるいは展開したキーワードの多くは、ネーミング・コンセプトの一部分だけを表現するものであって特性の伝達機能の発揮には不十分であるのが普通ですし、単なる形容詞や普通名詞である場合が多いため、特に商標権取得に当たっては商標法3条1項(商標の本質的機能である自他商品・サービス識別機能の欠如)に該当し、そうでない場合でも、業界にもよりますが、すでに他社が登録済みである場合が多いのが実情です。
そのため、多くの場合、何らかの形で「造語」して、ネーミングを案出する作業が必要となります。なお、具体的な造語の方法は、いくつかのパターンに分類できますので、パターンごとに事例を挙げて、次回から数回にわたってお話しします。4.言語調査
前々回にお話ししましたように、特にネーミングする商品・サービスが海外展開を想定している場合には、案出したネーミングが、外国人が接してもイメージに違和感がなく、ネガティブな意味がないものであることを事前に確認しておく必要があります。5.商標調査
造語により案出したネーミングの段階で、商標調査を行います。単に、同一・類似の先行事例を発見するだけでなく、他人の登録商標と同一または類似(商標法4条1項11号に該当)する可能性が高い引例を発見した場合には、拒絶理由を回避できる可能性を高めるための修正・変更を行う必要があります。6.ネーミング案(複数)決定
ネーミング案を複数決定します。適当なネーミング案の数は一概に決められませんが、実際には余り多すぎると絞り込み作業がむずかしくなりますので、似通ったものは可能な限り整理し、多くても20件、できれば10件以内とすることが望ましいです。
また、造語等により案出されたネーミング案の多くは、ネーミング・コンセプトの柱のいずれかとの関連性が強いグループを形成する場合が一般的です。その場合、どうしても造語しやすいキーワードに基づくネーミング案が多数できてしまい、特定のグループに偏るという傾向があります。
ネーミング案の絞り込み等の作業においては、できるだけ先入観を形成しない配慮が必要ですから、各グループに属するネーミング案はなるべく偏らないことが望ましいですが、どうしても大きな偏よりが生じる場合は、前述のネーミング・コンセプトの優先順位に基づき、順位の低いネーミング・コンセプトに基づくネーミング案ばかりが多くならないよう配慮する必要があります。