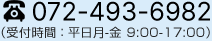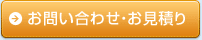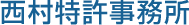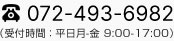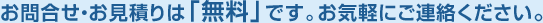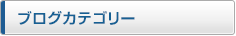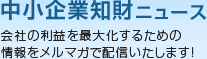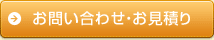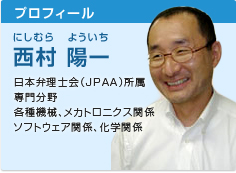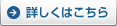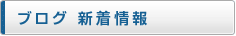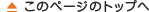ネーミング(5)
2013.05.29 10:00
今回は、前回に引き続き、ネーミングの案出作業を構成している 3.ネーミング(造語)作業、4.言語調査、5.商標調査、6.ネーミング案の決定についてお話します。
3.ネーミング(造語)作業
前回お話ししましたプロセスで集めたキーワードをもとに、ネーミングの案出作業を行います。キーワードがそのままの形でネームとしての要求条件を満たし、商標登録も可能な場合もまれにはありますが、現実には、抽出あるいは展開したキーワードの多くは、ネーミング・コンセプトの一部分だけを表現するものであって特性の伝達機能の発揮には不十分であるのが普通ですし、単なる形容詞や普通名詞である場合が多いため、特に商標権取得に当たっては商標法3条1項(商標の本質的機能である自他商品・サービス識別機能の欠如)に該当し、そうでない場合でも、業界にもよりますが、すでに他社が登録済みである場合が多いのが実情です。
そのため、多くの場合、何らかの形で「造語」して、ネーミングを案出する作業が必要となります。なお、具体的な造語の方法は、いくつかのパターンに分類できますので、パターンごとに事例を挙げて、次回から数回にわたってお話しします。4.言語調査
前々回にお話ししましたように、特にネーミングする商品・サービスが海外展開を想定している場合には、案出したネーミングが、外国人が接してもイメージに違和感がなく、ネガティブな意味がないものであることを事前に確認しておく必要があります。5.商標調査
造語により案出したネーミングの段階で、商標調査を行います。単に、同一・類似の先行事例を発見するだけでなく、他人の登録商標と同一または類似(商標法4条1項11号に該当)する可能性が高い引例を発見した場合には、拒絶理由を回避できる可能性を高めるための修正・変更を行う必要があります。6.ネーミング案(複数)決定
ネーミング案を複数決定します。適当なネーミング案の数は一概に決められませんが、実際には余り多すぎると絞り込み作業がむずかしくなりますので、似通ったものは可能な限り整理し、多くても20件、できれば10件以内とすることが望ましいです。
また、造語等により案出されたネーミング案の多くは、ネーミング・コンセプトの柱のいずれかとの関連性が強いグループを形成する場合が一般的です。その場合、どうしても造語しやすいキーワードに基づくネーミング案が多数できてしまい、特定のグループに偏るという傾向があります。
ネーミング案の絞り込み等の作業においては、できるだけ先入観を形成しない配慮が必要ですから、各グループに属するネーミング案はなるべく偏らないことが望ましいですが、どうしても大きな偏よりが生じる場合は、前述のネーミング・コンセプトの優先順位に基づき、順位の低いネーミング・コンセプトに基づくネーミング案ばかりが多くならないよう配慮する必要があります。ネーミング(4)
2013.05.22 10:00
今回からは、ネーミングの案出作業についてお話します。
ネーミングの案出作業は、[キーワードの抽出]→[キーワードの展開]→[ネーミング(造語)作業]→[言語調査]→[商標調査]→[ネーミング案の決定] という流れになります。今回は、1.キーワードの抽出、2.キーワードの展開について説明し、次回は、3.ネーミング(造語)作業、4.言語調査、5.商標調査、6.ネーミング案の決定について説明します。
1.キーワードの抽出
ネーミング・コンセプトから、想起されるキーワードを発案するプロセスです。キーワードは、一般的に、日本語のほか基本的な英語が中心となります。ここでは、ネーミング・コンセプトから逸脱しない範囲で、可能な限り様々な視点から、自由にキーワードを発案し、ネーミング・コンセプトの「柱」ごとに分類・整理します。
このプロセスでは、商標調査により、同種の商品・サービスについての商標出願や商標登録の事例を調べ、同様のネーミング・コンセプトに基づくと思われる代表的なキーワードを抽出することが重要です。
最終的なネーミングは先行事例と類似することを避けねばなりませんが(特に、他人の登録商標に類似する場合は、他人の商標権を侵害することになりますので、注意してください。)、ネーミング・コンセプトが共通の先行事例に多用されるキーワードは、やはり需要者の反応が良いものが選ばれていますから、次の「2.キーワードの展開」の材料としては有益な情報と言えますので、「素材」としての有力なキーワードは押さえておく価値があるといえます。2.キーワードの展開
次に、抽出したキーワードを、前回お話ししました「よいネーミング」の条件である機能性(読みやすい、言いやすい、聞き取りやすい、覚えやすい)を念頭におきながら他のワードへと展開します。一般には次のような方法で展開する場合が多いです。
1.同義語、類似語への展開
例)「美しい(beatiful)」
→(日本語)可憐、美麗、綺麗 等、
(英語)pretty、lovely、elegant、bonny 等
2.他の言語への展開
例)「美しい(beatiful)」
→bello(伊)、schon(独)、beau(仏)、hermoso(西)、漂亮(中) 等
3.象徴語、連想語への展開
例)「美しい(beautiful)」
→Venus(ローマ神話)、Freya(北欧神話) 等
このプロセスでは、ヒット商標の事例を調べることにより、キーワードの展開作業へのヒントを見つけることも重要です。ネーミング(3)
2013.05.15 13:11
今回はよいネーミングについてお話しします。
ビジネスにおいて「よいネーミング」とは、究極的には商品やサービスが「継続的に売れる」事に資するネーミングです。
インパクトの高いネーミングで爆発的にヒットする商品やサービスもありますが、商品やサービスの内容、品質が伴っていない場合は、売上はやがて低下しますし、短期的なインパクトの高いネーミングほど、飽きられやすく、より新奇なネーミングの競合商品の中に埋没するのも早いという傾向があります。
一方、ネーミングの失敗原因の中で多いのが、名付け側の「こだわり」や「思い入れ」が強すぎることによる「独善的なネーミング」です。こだわりや思い入れは、前回お話ししましたネーミングの機能の核となる重要なものではありますが、「継続的に売れる」ネーミングの案出に当たっては、常に商品やサービスの需要者への効果を想定しつつ検討し、再評価するプロセスを繰返すことが必要です。
以上を踏まえて、よいネーミングの条件を考えると、以下のようなものが挙げられます。①機能性(読みやすい、言いやすい、聞き取りやすい、覚えやすい)
メディア等を通じた広告で商品・サービスに最初に需要者が接した際に、読みやすく、言いやすく、聞き取りやすいネームが当然有利ですし、覚えやすいネームがその後の購買行動までの時間経過に耐えて記憶に残り、販売に貢献します。特に口コミの場合、ネームの覚え易さが伝播力を左右します。従って、この条件は良いネーミングの基本条件となります。
ただ、人間の記憶は必ずしもネームの単純性や馴染み易さとは相関しない場合があり、ある程度複雑なネームは異なる場合があります。②直感性(商品・サービスあるいは組織等のコンセプトやイメージを把握しやすい)
需要者はメディア等を通じて日々多数の商品・サービスとそのネームに接しているため、ネームがその注意を喚起して関心を引き付けるためには、需要者のニーズやウオンツと商品・サービスのコンセプトやイメージとの関連性を瞬間的に直感させるネームが有利です。
言い換えれば、需要者は多数の商品・サービスのネームに接する中で、無意識に、直感によって自分に関係のありそうなものとそうでないものを分別しています。従って、ネーミングは商品・サービスや提供企業などのコンセプトやイメージを直感的に把握させるものが望ましいといえます。
環境や高齢化への関心が高まりを反映して「エコ」や「シルバー」「シニア」といった文字を含むネーミングが増加しているのも、この直感性に訴える効果を狙ったものと思われます。③耐久性(時間経過により色褪せない、社会環境や流行に左右されにくい)
ネーミングはその時代の社会性や流行を反映し、いわゆる「旬」のワードが好んで取り入れられる傾向がありますが、社会環境変化のスピードが速まっているために「廃れ」も早くなっています。また、人気の高いワードが類似する競合ネームが急速に増加しますので埋没も早まり、需要者に飽きられやすくなります。
特に、企業名のネーミングでは、事業の多様化や転換により、ネーミングが企業コンセプトと剥離する可能性もたかまります。
商標に代表されるネームは、継続的な使用により信用を化体すべきものですから、ネーミングにおいては社会環境や流行に左右されず、時代を超えて色褪せないという視点も重要です。
ただ、この観点も、対象物のライフスパン(商品寿命)やターゲットとする需要者の特性を踏まえる必要があり、商品・サービスの販売計画や広告計画を念頭に置いたネーミングが重要となります。④個性(人の心に鮮烈な印象を与え、記憶に残りやすい)
他との識別機能を発揮するためには、ネーミングには個性が必要です。ただ、ネームに接した需要者が受ける印象は主観的なものであり、前述のマーケットのセグメントや商品・サービスのジャンルにより大きく左右されます。
あるセグメントの需要者にとって特定の商品・サービスのジャンルにおいて好ましい印象を与える個性的なネームも、異なるセグメントやジャンルにおいては悪印象を与えることも多いため、特に個性的なネームを採用する場合は、需要者のターゲットによる施行や商品・サービスのジャンルにおける先行事例についての十分な調査検討が必要となります。⑤国際性(外国人が接してもイメージに違和感がなく、ネガティブな意味がない)
海外市場も視野に入れた商品やサービスの場合、国際的に通用するネーミングが要求されます。英語等の外国語を用いたネーミングの場合、日本国内で一般的に認識されているワードの意味とネイティブの需要者がそのワードから直感する意味とがズレている事例は数多くあります。また、日本語のワードを使用したネームの場合、当該日本語の発音や表記が、海外市場では社会的・宗教的に禁忌されているワードの発音やイメージに合致・類似するケースもありますから注意が必要です。
例えば、「近畿」の二文字を発音通りローマ字表記した「Kinki」が、英語では「奇妙な」の意味を持つ「Kinky」と似た発音になるため忌避されることはよく知られていいますが、「雌鶏」の文字や図柄を商標に用いた場合、中国では「鶏」が「妓」と同じ「ジー」といったケースもあります。
その他、海外市場で登録商標となっているネームと同一・類似のネーミングは当然採用できませんが、登録商標でなくとも海外の特定地域で普通名称・慣用商標となっているワードも、当然避ける必要がある場合があります。⑥登録性(商標登録要件を具備している)
商品やサービスのネーミングである以上、商標登録要件を満たしていることが必要です。特に販売拡大の局面では、他社による同一又は類似の登録商標の出現により事業そのものに支障を生じるリスクが想定されます。最近の特定国による、いわゆる「先回り商標権取得」の頻発傾向も踏まえ、事業展開の計画を念頭に置いて、国内・海外での商標権取得に耐え得るネーミングを選択することが必要です。ネーミング(2)
2013.05.08 10:00
今回はネーミングの機能についてお話しします。
ネーミングの目的は情報発信ですが、その機能は大きく以下のように分類できます。
①他との識別機能
他との識別機能はネームの必須機能であり、商法上の自他商品役務等識別機能の根幹を成す機能です。需要者やステークスホルダー(特に取引者)における他社の商品やサービスとの混同を防ぎ、機会損失や不利益を防止する機能で、識別力を発揮させるには特徴的な外観や称呼による他との差別化が重要となります。②特性の伝達機能
ネーミングの目的から、やはり必須に近い機能であり、対象物のコンセプトや特徴、魅力を需要者に的確に伝えるものです。短いネームに対象物の魅力を凝縮できれば需要者の合理的な購買意思決定において競争優位に立てる可能性が高くなります。
ただ、伝達すべき特性情報のレベルは、ネーミングの対象物の市場におけるポジションにより異なります。提供者の知名度が低い場合、あるいは対象物自体が新規性の高いものである場合には、伝達すべき特性は具体性・直接生・分かりやすさが重要となりますが、提供者の知名度が高い場合(ブランドが確立している場合)や成熟市場に属する商品やサービスの場合になどにおいては、象徴性・直感生がより重要となり、分かりやすさの重要性は相対的に低下する傾向があります。③イメージの訴求機能
最近のネーミングでは極めて重視される機能です。マーケットのセグメント化の傾向が進んだ近年においては、商品のターゲットとなる需要者に応じて、その属する社会的階層、ライフスタイル、消費性向、流行などを踏まえて、それらに適合する言葉(語彙)、音感、字体、シンボル等を選択し、対象となるセグメントの需要者が反応し、好感を持つイメージを形成することが要求されます。④アイデンティティの構築機能
商品やサービスよりも提供者(企業)の理念やコンセプトを需要者に的確に発信して、信頼感や安心感、優越感を感じさせることで需要者に良好なイメージを持ってもらう機能です。アイデンティティの構築には一貫性や統一性が有効であるため、ネーミングにおいては「核」となる言葉を定め、それを拡張、展開、発展させる形で求心力のあるネームを考えていく方法が一般的です。ネーミング(1)
2013.05.01 10:00
これから数回にわたってネーミングについてお話しさせていただきます。
1.ネーミングとは
まず、ビジネス社会における「ネーミング」は、何らかの対象(商品、サービス等)に適切な「ネーム(名称)」を考案して与える作業であり、主にその対象物の需要者(消費者)やステークホルダー等に対する「情報発信」を目的としています。2.ネーミングの分類
ビジネスにおけるネーミングは、大きく以下のように分類できます。①商品又はサービスの名称
商品又はサービスの名称は、複数の商品(サービス)群に共通して使用する「シリーズ名」と、個別の商品(サービス)毎に付される「アイテム名」に分かれる場合があり、それらを単体で、あるいは組み合わせて使用することがあります。また、商品(群)やサービス(群)を互いに識別するための文字や記号が付加される場合もあります。
②組織(会社、団体、機関、店舗等)の名称
組織の名称には、いわゆる法人名や屋号のほか、近年は地域名や施設名も含まれます。
③ブランド名
ブランド名は、一般的には複数の商品(サービス)群に共通して使用する包括的な上位名称で、組織の名称自体がブランド名となっている場合も多くあります。ブランド名には、従来の特定企業の「事業ブランド名」のほか、近年は連携する複数企業が共通して使用する「企業横断ブランド名」も増えています。
「事業ブランド名」としては、例えば、KDDIの移動体通信事業ブランド「au」、花王の化粧品ブランド「ソフィーナ」等が該当します。
また、「企業横断ブランド名」としては、例えば、アサヒビール、近畿日本ツーリスト、トヨタ自動車等、業種を越えた複数の企業が共通して用いるブランド名「Will」があります。
④コミュニケーション名
コミュニケーション名は、主たる名称を補完する補完的名称(愛称)であり、サブネームやペットネーム、キャラクターネーム、スローガンなどがこれに当たります。
例えば、「日本電気株式会社」の場合、「NEC」がこれに該当します。
サブネームやペットネームは主たる名称に必要に応じて付加して使用することでその情報発信力を補完するもので、サブネームは商品(サービス)の特性を補足的に表示し、ペットネームは需要者(消費者)に親しみやすさ等の印象を喚起するイメージ的なものが多く見られます。
キャラクターネームは、商品(サービス)とは別に設定した架空又は実在のキャラクターの名称で、それを単体あるいは商品(サービス)名に付加して使用し、キャラクター自体が有する知名度による商品(サービス)の顧客誘因力の強化を図るものです。
スローガンは、主にブランドの将来的な方向性を示唆するメッセージ的な表現であり、企業名とのシナジー効果の発揮を意図するものが多く見られます。例えば、トヨタの「Drive Your Dreams.」がこれに該当します。
⑤機能名・特性名
近年のネーミングの新たな傾向として、商品・サービス名やブランド名とは別に、商品・サービスの機能や特性を表し、これを共通の機能や特性を有する複数の商品・サービスに横断的にサブネームとして使用するネーミングが増えています。例えば、シャープ株式会社のイオン発生機能の搭載商品群に使用されている「プラズマクラスター」がこれに該当します。こうした機能名・特性名は、新機能に関する技術を特許出願する際に、その機能を搭載する商品の展開に当たり商標登録について検討する必要があります。ネーミングを検討する際には、まず、当該ネームが、ビジネスにおいて上記のどの役割を果たすものとするかを検討することが望ましいと思われます。
TPP参加による知財関連分野への影響 「模倣撲滅 中韓に圧力も」
2013.04.24 14:28

環太平洋経済連携協定(TPP)交渉では、知的財産も重要なテーマとなっている。著作権や特許権などを守るルールや、模倣品などの取り締まりについて協議している。コピー商品の横行や技術流出に悩む日本企業にとって、重要な分野と言える。
TPP交渉で知的財産保護のルールが整備されれば、アジア太平洋地域の基準となる公算が大きい。そうなれば、中国や韓国といった交渉に参加していない国など「周辺地域に圧力として波及する」(政府高官)との見方もある。
交渉参加国の中では、米国が知的財産保護に熱心だ。すでに薬の特許強化や、著作権が及ぶ期間の延長などを提案している。
薬の特許権が強化されると、特許切れの後、他の製薬会社が同じ有効成分で作る安価な「後発医薬品(ジェネリック)」を販売しにくくなるとの指摘がある。
読売新聞 2013年4月19日 朝刊
最近、TVや新聞等でTPP参加による農業分野や国民皆保険制度への影響が話題となっていますが、知財関連分野にも影響があるようです。2011年2月10日付の流出文書(米国提案)によると、米国が参加国に対して知的財産権の保護強化を要求してくることが予想されています。
具体的には、以下のような要求等が含まれているようです。
<著作権の保護期間の延長>
「死後50年」から「死後70年」に延長しようというものです。
TPP交渉参加国では既に70年が多数派のようです。
<著作権侵害の非親告罪化>
現在、日本では、警察が海賊版のアップロードや販売を摘発しても、著作権者などの被害者が告訴しなければ著作権侵害を罪に問うことができませんが、非親告罪化すると著作権者の意志に関係なく起訴したり処罰したりできるようになります。
<法定損害賠償金の導入>
法定損害賠償とは、実損害の有無の証明がなくても、裁判所が(ペナルティ的な要素を含んだ)賠償金額を決められる制度です。TPP交渉において、こういった米国の知財保護要求が認められますと、国内で安価に入手できているコンテンツが手に入りにくくなるというデメリットはあります。しかしながら、日本も、米国同様、生み出した知的財産で利益を上げていかなければならない時代に突入したことを考えると、知的財産権の保護強化は日本にとっても好ましいことであり、世界に通用する価値ある知的財産を生み出すことができるか否かが今後の日本を左右する重要なポイントになると考えます。
弁理士 西村陽一
インド VS 欧米 「薬特許」紛争 スイス大手の申請認めず
2013.04.15 14:19

インド最高裁が、スイス製薬大手「ノバルティス」の抗ガン剤の特許を認めない判決を下し、波紋が広がっている。特許を安易に認めていけば、成分が同じ、より安価な薬の普及を阻害し、貧困層の健康に悪影響を及ぼすとするインドや発展途上国と、特許の侵害は新薬開発の停滞に直結するという欧米の大手製薬会社の主張は平行線をたどるばかりだ。
読売新聞 2013年4月13日 朝刊
医薬特許は人命に関わる場合がある点で、機械分野、電気分野等の他の特許と同じように取り扱うことができないといえます。従って、製薬会社と世界の低所得層との利害対立を如何に調整するかということが重要な課題であると考えます。
確かに、新薬を安く手に入れることができれば治療の幅が広がりますので、低所得層にとっては好ましいことですが、製薬会社は莫大な投資を行って医薬品を開発していますので、その投資を回収して大きな利益を上げることができなければ、製薬会社に新薬を開発するインセンティブが働かず、新薬の開発が進まないという問題が出てきます。
こういった問題を解決するために、製薬会社が国毎に新薬の価格を段階的に設定するということも提案されていますが、こういったやり方では、新興国において安い価格で販売された新薬が新興国から先進国に流入し、新薬の値崩れが起こるというおそれがあります。つまり、新興国から先進国に安い新薬が流入しないように、どうすれば、世界の低所得層だけにジェネリック医薬品の価格で新薬を提供できるかということがポイントになります。
例えば、次のような仕組みではいかがでしょうか? 先進国と新興国とで新薬の価格設定を変えるのではなく、世界中同一価格で新薬を販売し、製薬会社が、その販売数に応じて新興国の政府にジェネリック医薬品との価格差分を還元し、その国の医療制度の中で、その国の国民がその国の医療機関等を通じて新薬を実際に使用したときだけ、新薬をジェネリック医薬品の価格で提供できるようにするという仕組みです。
製薬会社としても、市場規模の大きいBOPビジネスを如何に考えるかが重要であり、新興国とwin/winの関係を構築できるような優れたビジネスモデルを提案していくことができるかが、今後の鍵になるものと考えます。
弁理士 西村陽一
第6回 商標の登録要件(3)
2013.04.10 10:00
前回は、二つ目の登録要件のうち、拒絶理由として最も頻繁に採用されている要件「他人の登録商標と同一・類似範囲にある商標は登録を認めない」についてご説明しましたので、今回は、その他の要件について簡単にご説明します。
以下に示す商標は登録が認められませんので、商標を採択する場合はご注意ください。
1.国旗、菊花紋章、勲章、褒章または外国の国旗と同一または類似の商標
2.パリ条約の同盟国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣が指定するものと
同一または類似の商標
3.国際連合その他の国際機関を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するも
のと同一または類似の商標
4.白字赤十字の標章、赤十字の名称、ジュネーブ十字の名称と同一または類似の商
標
5.国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって、営
利を目的としないものまたは公益に関する事業であって営利を目的としないも
のを表示する標章であって著名なものと同一または類似の商標
6.公序良俗を害するおそれがある商標
7.他人の肖像、氏名、名称、著名な雅号、芸名、筆名、これらの著名な略称を含む
商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
8.博覧会の賞と同一または類似の標章を有する商標
9.他人の周知商標と同一または類似の商標であって、同一または類似の商品に使用
するもの
→特許庁がインターネットで提供している特許電子図書館中の「日本国周知・著
名商標検索」でこれらの商標を検索することができる。
10.種苗法第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一または類
似の商標であって、その品種またはこれに類似する商品、役務について使用する
もの
11.他人の業務に係る商品役務と混同を生ずるおそれがある商標
→著名な商標を非類似の商品、役務に使用した場合等が該当する。
12.商品の品質または役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
→その品質又は質がその商品又は役務に現実に存在すると否とを問わず、その商
品が有する品質又は役務が有する質として需要者において誤認される可能性
がある場合は該当する。
13.ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示
14.商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状
15.他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標
→外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されていない
ことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り的に出願したもの、又は
外国の権利者の国内参入を阻止し若しくは代理店契約締結を強制する目的で
出願したもの等が該当する。弁理士 西村陽一
中韓特許和訳システム 政府構築へ 企業、無料で検索
2013.04.03 10:00

政府は2013年度から、中国と韓国で出願され認められた特許を日本語に翻訳し、企業関係者などが自由に閲覧・検索できるデータベース作りに着手する。中国や各国でライバル企業が特許を出願した場合、現地の言葉で書かれた特許内容を性格に理解するのは多くの日本企業にとって困難を伴う。このためライバル企業がどのような特許を出願・保有しているかを迅速に把握し、日本企業が知的財産を巡る紛争に巻き込まれることを防ぐ。13年度はまず約20億円の予算を投じ、今後数年かけて順次、でデータ蓄積を図る。
読売新聞 2013年3月4日 朝刊
現在、世界の特許文献において、中国文献が急増しており、企業にとって、中国文献へのアクセス性をいかに担保するかということが喫緊の課題となっている。特許庁は、このような急増する中国文献への対応として、日本語によるアクセス性を向上させるために、2013年3月19日より(独)工業所有権情報・研修館の特許電子図書館(IPDL:Industrial Property Digital Library)を通じて、機械翻訳を利用して作成した中国実用新案和文抄録データの検索・照会サービスを開始している。
具体的には、特許電子図書館のトップページを開き、検索メニューの「特許・実用新案検索」から「3.公報テキスト検索」を選択し、公報種別で、「中国特許和文抄録」、「中国実用新案機械翻訳和文抄録」のチェックボックスにチェックを入れた状態でテキスト検索を実行すると、中国特許和文抄録や中国実用新案機械翻訳和文抄録も併せて検索することができるようになっている。
また、中国出願の公開番号等が分かっている場合は、検索メニューの「特許・実用新案検索」から「10.外国公報DB」を選択し、発行国・機関の中国(CN)の入力欄において、所定の入力形式に従って文献番号等を入力すると、公開特許和文抄録、実用新案小海翻訳和文抄録を見ることができるようになっている。弁理士 西村陽一
MBA学位取得しました。
2013.03.27 10:00
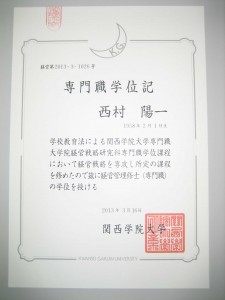
今月の16日に学位授与式があり、経営管理修士(MBA)の学位を取得いたしました。
2年前(2011年)の4月に、関西学院大学 専門職大学院 経営戦略研究科(ビジネススクール)に入学し、今年の3月までの2年間、経営の勉強をしてまいりました。仕事をしながらの勉強は大変でしたが、それまで知らなかった様々な知識に触れることができ、非常に刺激を受けました。
最後の半年は、「経営」、「マーケティング」、「ファイナンス」、「テクノロジー・マネジメント」、「アントレプレナー」の5つのプログラムから1つのプログラムを専攻すると共に、その専攻プログラムに沿って自らのテーマを決めて研究をし、その成果を論文として提出しなければなりません。
私は、ファイナンスプログラムを専攻し、既存商品や競合企業との関係で、新商品をどのようなタイミングで投入すれば、企業価値を最大化できるかということについて研究しました。
私は、技術を相手にする弁理士という仕事をしていますので、テクノロジー・マネジメントプログラムにしようかとも迷ったのですが、「ファイナンス」、「金融工学」、「ゲーム理論」、「企業ファイナンス」といった講義で、経営者の仕事は企業価値を最大化することで、その企業価値(事業価値)は計算によって求めることができるということを教えていただき、それが目から鱗で、最終的にファイナンスプログラムを専攻することに決めました。
「ファイナンス」という言葉からは「金融」というイメージがでてきますが、私が学んだ「ファイナンス」は、例えば、企業価値や事業価値といった様々な価値を計算することによって、経営者やマネジャーが少しでも的確な経営判断や意思決定を行うことができるようにするというものでした。例えば、M&Aでは買収しようとする企業の価値を求めなければ、いくらで買収すれば自社の企業価値を高めることができるかということも分かりませんし、企業が新規事業を立ち上げる際、その事業の価値を求めなければ、その事業をやるべきか否かの意思決定を行うことはできません。つまり、価値が分からなければ、勘で決めるしかありませんので、ギャンブル性が高くならざるを得ません。
企業経営においては、不確実な要素が数多く存在していますので、企業価値や事業価値というものを正確に計算することは不可能ですが、想定しうる種々な情報を使って価値を計算することで、経営判断や意思決定が大きく間違っていないというところまで持っていくことは可能であると考えられます。
今後は、私が学んだ「ファイナンス」、「リアルオプション」、「ゲーム理論」等の知識を企業経営、特に、中小企業の経営者の方に活用していただきたいと考えております。そこで、近々、「MBA弁理士のファイナンス講座」を開講し、ファイナンス理論等を少しずつ分かりやすくご説明していきたいと思っていますので、興味のある方は是非お読みください。
また、修士論文「リアルオプションとゲーム理論を用いた新商品投入の適正タイミングの考察」修士論文を書くに当たって、事業価値評価モデルを構築し、様々なパラメータを入力することによって、自社の新商品をどのようなタイミングで投入すればよいのかを計算することができるエクセルファイルを作成しておりますので、ご興味のある方はご連絡ください。エクセルファイルをお送りさせていただきますので、実際に使ってみて下さい。その際は、是非フィードバックをお願いします。
今後ともよろしくお願いいたします。
弁理士 西村陽一