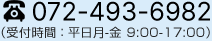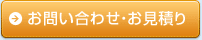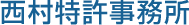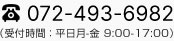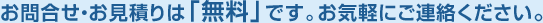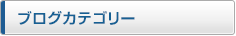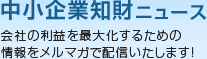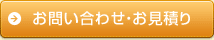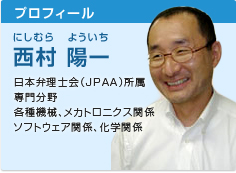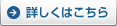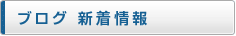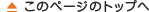特許調査(2)
2014.06.18 10:00
<特許データベースの種類>
特許データベースには、無料で利用できるものと有料のものとがあります。いずれも、特許庁から提供されるデータを収録していますので、検索されるデータ自体に差はありませんが、検索機能、検索データの出力機能、検索データの分析機能、検索データの保存機能等に差があるようです。つまり、有料のデータベースのほうが、使い勝手が良いということです。
無料で利用できるデータベースとしては、各国特許庁が提供しているデータベースがあり、インターネット接続環境があれば、誰でも利用することができます。
各国特許庁が提供しているデータベースは、基本的に審査官用のデータベースを、データ量、検索機能、出力機能を制限した状態で一般に開放しています。1)日本特許庁
特許電子図書館(IPDL) http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
※外国特許、国際特許出願についても検索できますが、出力機能に制限がかけられています。
2)米国特許商標庁
Patent Full-Text Database(PatFT, AppFT) http://patft.uspto.gov/
3)欧州特許庁
Espacenet http://worldwide.espacenet.com/
4)国際事務局(WIPO)
Patentscope http://patentscope.wipo.int/search/ja/search.jsf
※国際出願の検索(日本語で検索可)なお、欧州特許庁のEspacenetには、米国、日本、中国等の複数国のデータが収録されていますので、これからデータベースの使い方を学ばれる方は、Espacenetがお勧めです。
特許調査(1)
2014.06.11 10:00
<特許調査の種類>
特許調査には、その目的によって、「技術動向調査」、「侵害予防調査」、「特許性調査」、「無効資料調査」の4つに分類されます。
1)技術動向調査
企業が自社の研究開発のテーマを探索するための調査であり、公開特許公報、特許公報等の公報類における「要約」、「図面」に注目して調査を行います。
2)侵害予防調査
自社製品が他社の権利を侵害するか否かを調べる調査であり、特許公報の「特許請求の範囲(権利範囲)」や発明のポイントに注目して調査を行います。
3)特許性調査
特許権を取得するために特許出願したときの特許可能性を予測するための調査であり、自社の発明した技術に関連する技術が記載されていないかという観点で、公開特許公報の明細書及び図面全体に注目して調査を行います。
4)無効資料調査 : 他社の特許権を潰すための無効資料を収集するための調査であり、特許性調査と同様に、明細書全体及び図面に注目して調査を行います。また、特許公報類以外に、必要に応じて、技術論分、書籍、雑誌、製品カタログ等についても、調査します。
<特許データベース>
特許調査は、通常、特許データベースを用いて行います。
特許データベースでは、「書誌情報」、「技術情報」、「経過情報」等を取得することができます。
1)書誌情報
出願番号、公開番号、出願日、公開日、出願人・発明者、技術分類等の情報
2)技術情報
特許明細書(従来技術、発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段、発明の効果)、特許請求の範囲(権利範囲となる部分)、図面、要約書
3)経過情報
審査経過や審判経過に関する情報、年金(特許料)の納付状況、審査で引用された文献情報等
<特許データベースを用いた検索方法>
1)番号検索
公開番号や出願番号が分かっている場合は、番号検索により、該当する公開特許公報を取得することができ、経過情報についても入手できます。
従って、どのような内容で出願されているのか、出願経過がどうなっているのか、権利化されているのか、権利化されているのであれば、どうような権利が発生しているのかといった情報を取得することができます。
2)キーワード検索
出願人名で検索することにより、その企業が注力している技術分野の推移が分かります。
また、技術ワード等で検索することにより、その技術分野で技術力の高い企業を抽出することができると共に、その技術分野でどのような新技術が開発されているのかといった情報を取得することができます。
アップルとグーグル和解
2014.06.04 10:00
米アップルと米グーグルは16日、スマートフォンの技術に絡む一連の特許訴訟で和解した。双方がすべての訴訟を取り下げる。今後は、両者が特許関連訴訟の乱発防止に向けた米政府の規制強化に協力するという。
特許訴訟の乱発は多額の訴訟費用がかかるほか、自由競争の妨げになるとして、各国政府などから批判が高まっている。アップルは韓国サムスン電子とも大型の特許侵害訴訟を争っているが、サムスンはグーグルが提供する基本ソフト(OS)「アンドロイド」を搭載するスマホを製造していることから、アップルとグーグルの代理戦争との見方も多い。今回の和解がアップルとサムスンの訴訟にも影響するか、注目される。
読売新聞 2014年5月18日 朝刊アップルとグーグルは、5月16日に「相互の直接の訴訟をすべて取り下げることで合意した。今後両社は特許制度の改革のために協力」していく」という声明を発表しましたが、アップル陣営の企業やグーグル陣営の企業に対する訴訟を取り下げるわけではありませんので、アップルがサムスンを訴えている特許訴訟については取り下げの対象とはならず、今後も、両社間では熾烈な争いが続くものと思われます。
弁理士 西村陽一コンピュータ・ソフトウエアの保護(8)
2014.05.28 10:00
<コンピュータ・ソフトウエア関連発明の外国での権利化>
今回は、コンピュータ・ソフトウエア関連発明を外国(米国、欧州)で権利化するについてご説明します。
コンピュータ・ソフトウエア関連発明の特許要件(特に、保護適格性、発明の成立性)は、国によって異なるため、出願国によってどのような要件が課されるのかについて注意が必要です。特に、ビジネス方法やゲームルール等の人為的取り決めであると判断される可能性が高い主題を含む発明については、保護適格性や発明の成立性の判断基準が厳しい場合がありますので、留意する必要があります。
<米国における保護>
1.米国におけるクレームの保護的確性の動向
●1998年 State Street事件のCAFC判決
有用で、具体的かつ実体のある結果を生む主題がクレームされている場合は、ビジネスモデルであっても特許を受けることができる旨を判事。
●2008年 Bilski事件のCAFC判決
方法クレームの保護的確性は、Machine or Transformation(MOT)テストのみに基づいて行うべきである旨を判事。
→クレームの中に特定の機械との結びつきや特定のものを異なる状態へ変化させることが記載されていることが必要。
●2010年 Bilski事件の最高裁判決
MOTテストが有効なテストであることを認めた上で、MOTテストは唯一の基準ではない旨を判事。
ただし、MOTテスト以外に用いることができる具体的基準については示さなかった。
●2013年 CLS Bank vs ALICE事件のCAFC判決
本事件で争われた、ハードウエア要素を明示的には含まないビジネス方法のクレームは抽象的であると結論したが、クレーム主題が「抽象的アイデア」か否かを判断するための具体的基準を示さなかった。
以上のように、2013年5月時点においては、米国において、クレームされた主題が「抽象的アイデア」か否かを判断するための具体的な基準は明らかにされておりません。
→米国においては、クレームが特許の対象であるか否かを判断するための基準は明確ではありません。
2.米国に対してコンピュータ・ソフトウエア関連発明を出願する際の留意事項
①Bilski事件の最高裁判決は、MOTテストを否定していないため、MOTテストをクリアすれば、保護的確性は認められるものと考えられます。
②日本における発明の成立性要件を満たす程度のハードウエア要素を含むクレームは、米国でもMOTテストを満たすとして保護適格性を満たす蓋然性は高いものと考えられます。
従って、米国にコンピュータ・ソフトウエア関連発明を出願する際は、日本における発明の成立性を満たす程度のハードウエア要素を含むクレームを少なくとも入れておくことが望ましいといえます。
<欧州における保護>
欧州特許条約(EPC)52条には、コンピュータプログラム自体(as such)は特許を受けることができないと規定されています。
EPC52条の非特許条項からコンピュータプログラムを外すEU指令案が上程されましたが、2005年の欧州議会がこれを否決されました。
コンピュータプログラム自体は著作権で保護されると共に、プログラムをコンピュータに実装した技術は、特許の対象になります。
従って、プログラムで制御されるコンピュータ、プログラムで制御される処理方法は、所定の要件を満たせば、特許を受けることができます。
1.欧州(EPC)の審査手法
①保護適格性
審査ガイドラインには、「クレームされた主題が明らかに技術的な性質を有さない場合には、52条(2) 及び(3)に基づき拒絶すべきである。」と記載されています。
ただし、この保護的確性の判断は比較的緩く、コンピュータや端末等のハードウエア要素がクレームに含まれていれば、52条の非特許対象には該当しません。
②進歩性
ヨーロッパ特許庁におけるコンピュータ・ソフトウエア関連発明ついての進歩性の判断基準は、日本や米国とは少し違っています。
まず、クレーム全体から見た技術的性質 (technical character)を特定します。
そして、クレームの中で特定された技術的性質のみが、進歩性の評価対象となり得ます。
例えば、コンピュータシステムの部分は従来の公知のコンピュータシステムと同じで、ビジネス方法のみが新規なコンピュータシステムのクレームについては、ビジネス方法の部分というのは技術的性質ではないので、進歩性の評価対象とはならず、クレーム全体の進歩性が否定されます。
2.欧州に対してコンピュータ・ソフトウエア関連発明を出願する際の留意事項
上述しましたように、欧州では、ビジネス方法のみが新しいコンピュータ・ソフトウエア関連発明は、進歩性が否定される可能性が高いので、そういったクレームのみを含む出願を欧州にするべきか否かについては、慎重に検討する必要があります。
TPP知財分野合意へ 日米など12カ国著作権保護「70年」
2014.05.21 10:00

太平洋経済連携協定(TPP)交渉に参加している日米など12か国が、音楽や小説の著作権の保護期間を70年に統一することで合意する見通しになった。新薬を開発した企業が市場を独占できる「データ保護期間」は、先進国は10年程度、新興国は5年以下と、新興国側に配慮した案で決着する見込みだ。難航分野の一つである知的財産分野の交渉にめどがつき、TPP交渉全体が妥協へ向けてさらに前進する。
TPP交渉で、米国は、自国と同じ70年に統一することを提案していた。映画や音楽などを海外に輸出して著作権収入を長い間稼ぎたいためだ。これに対し、日本は関税協議で米国と対立していたため、交渉戦術上、最終的な判断は保留していたが、4月の日米協議の実質合意を受け、70年への統一に応じる方針に転じた。
ただ、日本は映画については例外的に保護期間を公開後70年としており、過去の名作映画などのDVD販売や放送・配信には大きな影響はないとみられる。
一方、マレーシアやベトナムなどの新興国は著作権料の支払いが増えることを懸念して70年への統一に反対していたが、交渉を主導する日米の足並みがそろったことで、異議を唱えにくくなった。新薬のデータ保護期間について米国が譲歩したため、著作権で新興国側が譲った面もある。
読売新聞 2013年9月14日 朝刊「データ保護期間」について、先進国は10年程度、新興国は5年以下で決着するようですが、医薬品等の「データ保護制度」について簡単に説明しておきます。
まず、医薬品等の一部の分野では、安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可等を得るにあたり所要の試験・審査等に相当の長期間を要するため、その間はたとえ特許権が存続していても、医薬品等を独占的に製造販売することができないといった問題があります。
このため、日本では、特許権の存続期間の延長制度が設けられており、医薬品の臨床試験や承認審査によって特許発明を実施できなかった期間を上限5年により補償(延長)しています。なお、本制度によって得られる医薬品特許の実質特許期間(EPL)は平均で約11年であるといわれています。また、新薬メーカーは、上述しましたように、規制当局による承認を得るために必要な試験を行う必要がありますが、その試験を行うための費用が高騰し、承認の取得もより困難になっていくにつれ、試験データそのものが、特許等の伝統的な知的財産権と同様の排他権による保護を与えることも可能なほど貴重な資産となってきています。
ジェネリック医薬品の申請者であるジェネリック医薬品メーカーが、新薬メーカーが販売承認を得るために規制当局に提供したデータを直接的又は間接的に使用することができるとすると、ジェネリック医薬品メーカーが新薬メーカーの行った努力に「ただ乗り」するという結果となり、両者間の公平性を欠くということで、新薬メーカーを保護するために、欧米においては、それらのデータに対し一定期間の保護を与えています。
一方、日本においては、このようなデータ保護制度はありませんが、新薬の承認後も引き続いて医薬品の調査を開発会社に行わせ、承認時に指定された調査期間(再審査期間)後に、その安全性等の再審査を行うという「再審査制度」があり、
先発医薬品が再審査期間中にある場合は、ジェネリック医薬品であっても承認申請にあたって先発医薬品と同等の資料が要求されるため、再審査が終了するまではジェネリック医薬品の承認申請は実質的にはできません。なお、現在、日本においても、このデータ保護制度の導入についてその検討が行われているようです。ここで、特許権の存続期間とデータ保護期間とのバランスが問題となってきます。
弁理士 西村陽一コンピュータ・ソフトウエアの保護(7)
2014.05.14 10:00
<コンピュータ・ソフトウエア関連発明の保護>
今回は、「ポイントサービス方法」というビジネス分野の発明を例に挙げながら、特許法上の「発明」に該当するか否かの判断がどのようになされるかについてご説明します。
<特許を請求する発明1>
テレフォンショッピングで商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、
贈与するポイントの量と贈答先の名前が電話を介して通知されるステップ、
贈答先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先の電話番号を取得するステップ、
前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先のポイントに加算するステップ、及び
サービスポイントが贈与されたことを贈答先の電話番号を用いて電話にて贈答先に通知するステップとからなるサービス方法。
<結論>
特許法上の「発明」には該当しない
<理由>
「電話」、「顧客リスト記憶手段」という手段を使用するものであるが、全体としてみれば、それらの手段を道具として用いる人為的取り決めそのものであり、「自然法則を利用していないもの」に該当するので、「発明」には該当しない
<特許を請求する発明2>
テレフォンショッピングで商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、
贈与するポイントの量と贈答先の名前がインターネットを介して通知されるステップ、
贈答先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先の電子メールアドレスを取得するステップ、
前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先のポイントに加算するステップ、及び
サービスポイントが贈与されたことを贈答先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈答先に通知するステップとからなるサービス方法。
<結論>
特許法上の「発明」には該当しない
<理由>
「インターネット」、「顧客リスト記憶手段」、「電子メール」という手段を使用するものであるが、全体としてみれば、それらの手段を道具として用いる人為的取り決めそのものであり、「自然法則を利用していないもの」に該当するので、「発明」には該当しない
<特許を請求する発明3>
テレフォンショッピングで商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、
贈与するポイントの量と贈答先の名前がインターネットを介してサーバーに入力されるステップ、
サーバーが、贈答先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先の電子メールアドレスを取得するステップ、
サーバーが、前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先のポイントに加算するステップ、及び
サーバーが、サービスポイントが贈与されたことを贈答先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈答先に通知するステップとからなるサービス方法。
<結論>
特許法上の「発明」に該当する
<理由>
サーバーが「顧客リスト記憶手段」を検索して贈答先の電子メールアドレスを取得すると共に、「顧客リスト記憶手段」に記憶されている贈答先のポイントに加算し、取得した贈答先の電子メールアドレスに対して通知を行うという処理を、ハードウエア資源であるコンピュータを用いて具体的に実現した情報処理システムの動作方法であり、「ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されたもの」であるから、「発明」に該当する
コンピュータ・ソフトウエアの保護(6)
2014.05.07 10:00
<コンピュータ・ソフトウエア関連発明の保護>
今回は、「ネットワーク配信記事保存方法」というビジネス分野の発明を例に挙げながら、特許法上の「発明」に該当するか否かの判断がどのようになされるかについてご説明します。
<特許を請求する発明1>
受信手段が、通信ネットワークを介して配信される記事を受信するステップ
表示手段が、受信した記事を表示するステップ、
ユーザが、該記事の文章中に所定のキーワードが存在するか否かを判断し、存在した場合に保存指令を記事保存実行手段に与えるステップ、
前記記事保存実行手段が、保存指令が与えられた記事を記事記憶手段に記憶するステップ
から構成されるネットワーク配信記事保存方法。
<結論>
特許法上の「発明」には該当しない
<理由>
「ユーザが、該記事の文章中に所定のキーワードが存在するか否かを判断し、存在した場合に保存指令を記事保存実行手段に与える」というステップは、人間の精神活動に基づいて行われる処理であり、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働することにより構築されたシステムの動作方法とはいえないから、「発明」に該当しない
※特定審査基準を適用した判断
<特許を請求する発明2>
受信手段が、通信ネットワークを介して配信される記事を受信するステップ
表示手段が、受信した記事を表示するステップ、
記事保存判断手段が、該記事の文章中に所定のキーワードが存在するか否かを判断し、存在した場合に保存指令を記事保存実行手段に与えるステップ、
前記記事保存実行手段が、保存指令が与えられた記事を記事記憶手段に記憶するステップ
から構成されるネットワーク配信記事保存方法。
<結論>
特許法上の「発明」に該当する
<理由>
記事の文章中に所定のキーワードが存在するか否かを判断し、存在した記事を保存するという処理が、保存判断手段、記事保存実行手段及び記事記憶手段という、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって実現されたシステムの動作方法であるから、「発明」に該当する
※特定審査基準を適用した判断
コンピュータ・ソフトウエアの保護(5)
2014.04.30 10:00
<コンピュータ・ソフトウエア関連発明の保護>
今回は、計算方法及び計算装置という数学分野の発明を例に挙げながら、特許法上の「発明」に該当するか否かの判断がどのようになされるかについてご説明します。
<特許を請求する発明1>
コンピュータを用いて、
自然数nとm(ただし、1≦n≦m<256)との乗算sを、
s={(m+n)2-(m-n)2}/4
によって計算する計算方法。
<結論>
特許法上の「発明」には該当しない
<理由>
数式の計算そのものであり、自然法則を利用していないので、「発明」に該当しない
※一般審査基準を適用した判断
<特許を請求する発明2>
コンピュータを用いて、
自然数nとm(ただし、1≦n≦m<256)との乗算sを、
s={(m+n)2-(m-n)2}/4
によって計算する計算装置。
<結論>
特許法上の「発明」には該当しない
<理由>
計算装置で計算するというだけでは、計算処理を実行するソフトウエアとハードウエア資源とが協働しているとはいえないから、「発明」に該当しない
※特定審査基準を適用した判断
<特許を請求する発明3>
自然数nとmを入力する入力手段(ただし、1≦n≦m<256)と、
演算手段と、
演算手段による演算結果sを出力する出力手段、
とを備えることによって、
s={(m+n)2-(m-n)2}/4
によって計算する計算装置。
<結論>
特許法上の「発明」には該当しない
<理由>
各手段(入力手段、演算手段、出力手段)が演算を実行するソフトウエアと協働していないから、「発明」に該当しない
※特定審査基準を適用した判断
<特許を請求する発明4>
自然数nとmを入力する入力手段(ただし、1≦n≦m<256)と、
K番目にk2の値が格納された二乗テーブル(ただし、0≦k<511)と、加減算器及びシフト演算器からなる演算手段と、
前記演算手段による演算結果sを出力する出力手段、
とを備え、
前記演算手段が前記二乗テーブルを参照して二乗の値を導出することにより、乗除算器を用いることなく、
s={(m+n)2-(m-n)2}/4
を計算する計算装置。
<結論>
特許法上の「発明」に該当する
<理由>
「前記演算手段が前記二乗テーブルを参照して二乗の値を導出することにより、」という記載によって、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働しているといえるので、「発明」に該当する
※特定審査基準を適用した判断
コンピュータ・ソフトウエアの保護(4)
2014.04.23 10:00
<コンピュータ・ソフトウエア関連発明の保護>
請求項に係る発明が特許法上の「発明」であるためには、「その発明は自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものである」ことが必要であり、特許法上の発明でない場合は、特許法第29条第1項柱書き違反として拒絶されます。
しかしながら、コンピュータ・ソフトウエア関連発明は、数学的なアルゴリズムやビジネスを行うための方法など、それ自体が自然法則を利用しない特徴に寄ってたつことが多いため、特許法上の「発明」であるか否かが問題となることがしばしばあります。
このため、コンピュータ・ソフトウエア関連発明については、特定技術分野の審査基準が設けられており、その審査基準において、「『ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている』場合は、ンピュータ・ソフトウエア関連発明が『自然法則を利用した技術的思想の創作』である」と記載されており、さらに、「『ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている』とは、ソフトウエアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は下降を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法が構築されることをいう。」と記載されています。
以下、審査基準に挙げられた具体例に基づいて、「ハードウエア資源を用いて具体的に実現」とは如何なる場合をいうのかについて説明していきます。
●ハードウエア資源を用いて具体的に実現されていない具体例(1)
<請求項に係る発明>
文書データを入力する入力手段、
入力された文書データを処理する処理手段、
処理された文書データを出力する出力手段を
備えたコンピュータにおいて、
上記処理手段によって入力された文書の要約を作成するコンピュータ。
上記請求項には、「入力された文書の要約を作成する処理」と、「処理手段」とがどのように協働しているのかが具体的に記載されていないため、ハードウエア資源を用いて具体的に実現」されているとはいえず、特許法上の「発明」に該当しない。
●ハードウエア資源を用いて具体的に実現されていない具体例(2)
<請求項に係る発明>
数式y=f(x)において、a≦x≦bの範囲のyの最小値を求めるコンピュータ。
「コンピュータ」を用いるということだけでは、y=f(x)の最小値を求める処理とコンピュータとが協働しているとはいえず、特許法上の「発明」に該当しない。
コンピュータ・ソフトウエア関連発明については、特定技術分野の審査基準に基づいて、発明の成立性が判断されると説明しましたが、一般の審査基準で発明の成立性が判断される場合もあります。
●一般の審査基準で判断される例
1.一般の審査基準に挙げられた「発明」に該当しないものの類型に該当する場合
(a) 経済法則、人為的取決め、数学公式、人間の精神活動
(b) 画像データ、運動会のプログラム、コンピュータプログラムリスト等の情報の単なる提示
2.一般の審査基準に挙げられた「発明」に該当するものの類型に該当する場合
(a) 機器等(例えば、炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク等)に対する制御を具体的に行うもの
(b) 対象の物理的性質又は技術的性質(例えば、エンジン回転数、圧延温度)に基づく情報処理を具体的に行うもの
→これらが請求項に記載されている場合は、特定技術分野の審査基準で記載されている「ハードウエア資源との協働」という要件は問われない
コンピュータ・ソフトウエアの保護(3)
2014.04.16 10:00
<コンピュータ・ソフトウエア関連発明の保護>
特許法第36条第4項第1号は、
「…発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 …その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」
と規定しています。これを実施可能要件といい、明細書の記載がこの要件を満たしていない場合は、同号違反として拒絶されます。
●コンピュータ・ソフトウエア関連発明について、上記実施可能要件を満足させるために、ソフトウエア処理を行うコンピュータの構成が周知のコンピュータと同じであれば、コンピュータの構成要素を全て図面等に表す必要はありませんが、ソフトウエアの処理がコンピュータのプロセッサやメモリ等のハードウエア要素によってどのように実行されるのかが分かるように実施形態を記載すればよいことになります。つまり、
1)課題を解決するためにどのようなデータが入力されるのか
2)入力データがどのように処理されるのか
3)処理結果がどのように出力されるのか
という処理の流れを機能的に複数の段階に分割し、それぞれの機能をブロック化してブロック図に表すと共に、それぞれの機能処理をステップとしたフローチャートを作成することが必要となります。なお、実施可能要件を満たすためには、処理の内容がブラックボックスにならないように、入力データから所望の出力データを得るまでの処理内容を具体的に説明しなければならないことに留意する必要があります。
○コンピュータ・ソフトウエア関連発明に特有の実施可能要件違反の例
(1)請求項に係る発明に対応する技術的手順又は機能が抽象的に記載してあるだけで、その手順又は機能がハードウエアあるいはソフトウエアでどのように実行又は実現されるのか記載されていない場合
例1:請求項に、数式解法、ビジネス方法、あるいはゲームのルールを実行する情報処理システムが記載されているにも関わらず、明細書に、これらの方法やルールをコンピュータ上でどのように実現するのか記載されていないため、請求項に係る発明が実施できない場合
例2:コンピュータの表示画面等を基にしたコンピュータの操作手順が説明されているものの、コンピュータの操作手順からは、そのコンピュータの操作手順をコンピュータ上でどのように実現するのかが記載されていないため、請求項に係る発明が実施できない場合
判決例 平成24年12月25日 知財高裁 平成24年(行ケ)第10053号
(2) 発明の詳細な説明の記載において、請求項に係る発明の機能を実現するハードウエアあるいはソフトウエアが機能ブロック図又は概略フローチャートで説明されており、その機能ブロック図又はフローチャートによる説明だけでは、どのようにハードウエアあるいはソフトウエアが構成されているのか不明確である場合
●従って、コンピュータソフトウエア関連発明の実施形態を記載する場合は、機能ブロックのそれぞれと、コンピュータのハードウエアとの関係を実施形態において説明する必要があります。具体的には、ある機能を実現するためのブロックに関してその機能を実現するための処理フローを記載すると共に、その処理を実現するためのプログラムをコンピュータのプロセッサに読み込まれて実行されること等を説明する必要があります。
(3) 請求項が機能を含む事項により特定されているが、発明の詳細な説明ではフローチャートで説明されており、請求項記載の機能とフローチャートとの対応関係が不明確である場合
例3:複数の機能手段から構成されるビジネス支援用情報処理システムとして請求項に記載されているにも関わらず、発明の詳細な説明にはビジネスの業務フローしか記載されておらず、請求項記載の機能手段と業務フローとの対応関係が不明確である結果、請求項に係る発明が実施できない場合
●このような記載不備の指摘を受けないためには、請求項に記載された機能手段がフローチャートのどの部分に対応するのかを実施形態において明確に対応づけて記載することが望ましく、また、機能ブロック図を追加して、どの機能ブロックがフローチャートのどの部分に対応するのかを説明することも有効です。