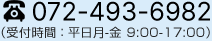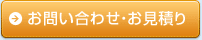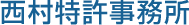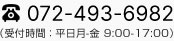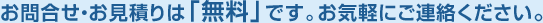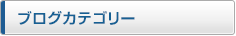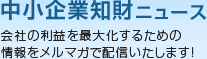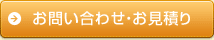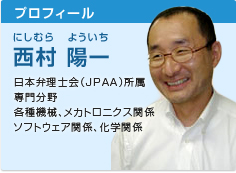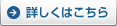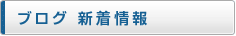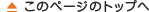不正競争防止法(5)
2014.02.12 10:00
<不正競争防止法の「混同惹起行為」とは >
1.「混同惹起行為」には、周知の他人の商品表示又は営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と他人とを同一の商品主体又は営業主体と誤信させる、いわゆる「狭義の混同惹起行為」だけでなく、緊密な営業上の関係や同一の商品化事業を営むグループに属する関係(親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係)があると誤信させる、いわゆる「広義の混同惹起行為」も含むものと解されています。
・日本ウーマンパワー事件
(最高裁 昭和58年10月7日判決 昭和57年(オ)第658号)
・フットボール事件
(最高裁 昭和59年5月29日判決 昭和56年(オ)第1166号)
・スナックシャネル事件
(最高裁 平成10年9月10日判決 平成7年(オ)第637号)
2.また、混同が実際に生じていなくても、混同が生じるおそれがあれば「混同惹起行為」に該当します。ただし、実際の裁判では、「混同が生じるおそれがある」との心証を裁判官に抱かせる程度に立証する必要があります。例えば、以下の事項が「混同のおそれ」の判断要素としてあげられます(実務相談 不正競争防止法(初版第1刷) 172頁 商事法務研究会)
・表示の著名性や識別力の程度
・周知表示と模倣した表示の類似の程度
・商品・営業の類似、顧客層の重なりなどの競合関係
・現実の混同の発生の有無
・模倣者の悪意の存否
3.また、混同を生じるかどうかについては、「混同惹起行為」が周知表示を有する他人の営業上の利益を害するだけでなく、取引秩序の混乱につながることから、「混同惹起行為」を禁止する趣旨は公正な競業秩序の形成維持にあるとして、一般取引者及び需要者の心理を基準とし、日常一般に払われる注意力をもって判断すべきであるとされています。
・オービックス事件
(知財高裁 平成19年11月28日判決 平成19年(ネ)第10055号)