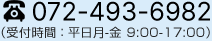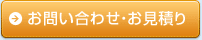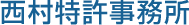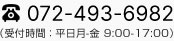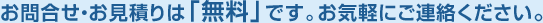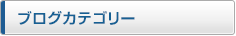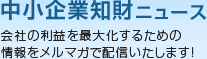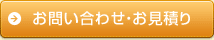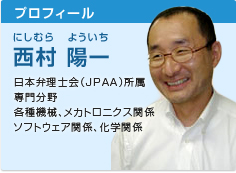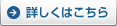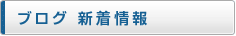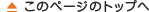不正競争防止法(11)
2014.03.28 11:23
<営業秘密侵害に関する裁判例で、秘密管理性はどのように判断されているか。>
不正競争防止法2条6項の「秘密として管理されている」というためには、「当該情報の保有者に秘密に管理する意思があり、当該情報について対外的に漏出させないための客観的に認識できる程度の管理がなされている」必要があります(会計事務所顧問先名簿事件 大阪地裁平成11年9月14日判決)。
そして、「客観的に認識できる程度の管理がなされている」というためには、通常、
①当該情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であることを認識できるようにしていること
②当該情報にアクセスできる者が制限されていること
が必要である、とされます(プロスタカス顧客名簿事件 東京地裁平成12年9月28日判決)。
また、要求される情報管理の程度や態様は、秘密として管理される情報の性質、保有形態、企業の規模等に応じて決せられるものとされます(小松一雄 不正競業訴訟の実務P.333)。
そして、営業秘密に関する事案は元従業員等が関与する場合がほとんどですが、裁判所が請求を認容した事案も、元従業員等の行為が自由競争の範囲を逸脱していると思われる場合に、元雇用主を救済するために、元雇用主の有していた情報のうちどこまで秘密として管理されていた営業秘密として保護できるかということを検討し、請求の当否を判断していると思われる場合も少なくありません。
そのような事情を反映して、秘密管理性等の営業秘密の要件、不正取得等の要件が全体的に勘案されています。したがって、裁判例における営業秘密の要件の検討に当たっては、個々の要件ごとに検討するとともに、事案全体を見て、相互の要件の関係も検討する必要があると指摘されています(上掲書p.343-344)。