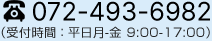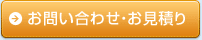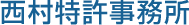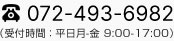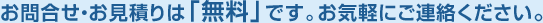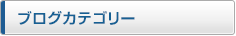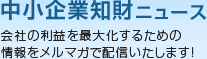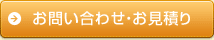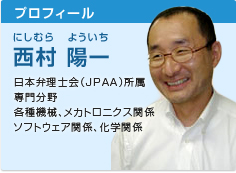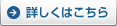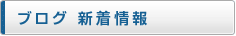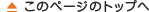不正競争防止法(8)
2014.03.05 10:00
<不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する「模倣」とは>
・不正競争防止法 第2条第1項第3号
他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
1.同法2条5項には、「模倣」を、「他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう」と定義しています。
2.「依拠」について
「依拠」については、原告被告間の製品の形態の同一性、発売日との関係、さらには原告と被告の取引関係の有無などを考慮して判断されています。また、原告商品がマスコミ等で多数取り上げられてヒット商品となった後に被告商品が発売されているような場合には、「依拠」していると認められる可能性が高くなります。
・たまごっち事件
(東京地裁 平成10年2月25日判決 平成9年(ワ)第8416号)
・レース付き衣服形態模倣事件
(東京地裁 平成19年7月17日判決 平成18年(ワ)第3772号)
3.「実質的に同一の形態」について
本号は、基本的には商品形態のデッドコピーを規制するための規定であり、類似の形態までは規制することができません。
・ドラゴンキーホルダー事件
(東京高裁 平成10年2月26日判決 平成8年(ネ)第6162号)
作り出された商品の形態が既に存在する他人の商品の形態と相違するところがあっても、その相違が僅かな改変に基づくものであって、酷似しているものと評価できるような場合には、実質的に同一の形態であるというべきであるが、当該改変の着想の難易、改変の内容・程度、改変による形態的効果等を総合的に判断して、当該改変によって相応の形態上の特徴がもたらされ、既に存在する他人の商品の形態と酷似しているものと評価できないような場合には、実質的に同一の形態とはいえないと判示した事例
・便座シート事件
(大阪地裁 平成20年7月17日判決 平成20年(ワ)第1637号)
需要者は、原告商品の購入を検討するに際し、内側切り目を意識し、その効用を予想するものと考えられ、原告製品における内側切り目は、商品購入の際の重要な考慮要素となるものと認められることから、被告製品には、原告製品の形態上の顕著な特徴である内側切り目が全く設けられていないから、その他の原告製品の形態上の共通点を考慮しても、原告製品と被告製品とが、実質的に同一の形態であると認めることはできないと判示した事例