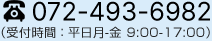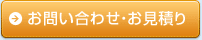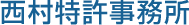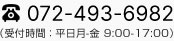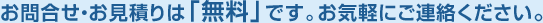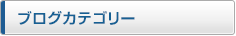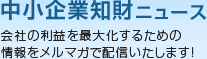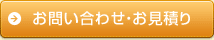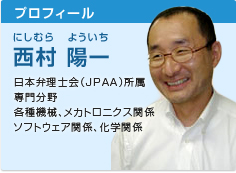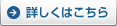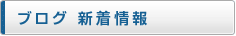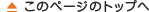NTTドコモ顧客流出止まらず 交渉5年 苦境でアップルと妥協
2013.09.18 10:00

日本では、ソフトバンクモバイルが2008年7月にiPhone(アイフォーン)を初めて販売したが、NTTドコモも同じ時期に米アップルと交渉を始めていた。
「NTTの研究所が持つ携帯電話に関するすべての特許を使わせてほしい」
アップルが交渉で、ドコモに突きつけた要求は、NTTグループにとって衝撃だった。当時、評価が定まっていなかったアイフォーンの販売と引き換えに、NTTが長年培ってきた特許の使用を求めるアップルの交渉姿勢にNTT側は不信感を強め、交渉は物別れに終わった。
その後も、ドコモはアップルとの話し合いを断続的に続けてきたが、両社の溝は埋まらなかった。ドコモは、米グーグル社の基本ソフトウェア(OS)「アンドロイド」を搭載したスマートフォンの販売に力を入れる。いったんはアイフォーンに依存しない戦略に傾きかけたが、11年10月にKDDI(au)が販売を始めると、ドコモからの顧客流出に拍車がかかった。
読売新聞 2013年9月14日 朝刊
ソフトバンクに続いてauがiPhoneを販売し始めると、ドコモからの顧客の流出に拍車がかかったようだ。
NTTドコモは、ソフトバンクがiPhoneを販売し始めた当りから、iPhoneの販売についてアップルと交渉を始めていたようだが、NTTの研究所が持つ携帯電話に関する全ての特許についてのライセンスを求めたアップル側の要求をのむことができず、結果的にiPhoneの導入が遅れたことがこういった状況を招いたといえる。
本事例は、オープンイノベーションの時代に入った今日、経営資源としての特許(技術)をどのように活用すればよいのかということを教えている。「虎の子」のインバーター技術を中国メーカーに提供する代わりに、「安く作る技術とそれによって得られる市場」を獲得したダイキンの成功例もあるように、技術の独占にこだわらずに、特許を含めた自社技術を如何に企業経営に役立てるのかが問われる時代に入ってきたといえる。
当時、iPhoneの評価が定まっていなかったという状況で、携帯電話に関するNTTの全保有特許についてアップルにライセンスを与えるという決断ができなかったという事情も理解できるが、iPhoneを導入したソフトバンクの躍進ぶりをみれば、もう少し早く対処すべきではなかったか、経営判断の難しいところであろう。
弁理士 西村陽一