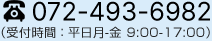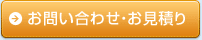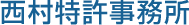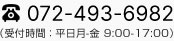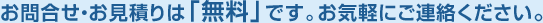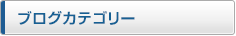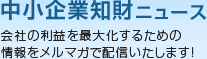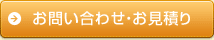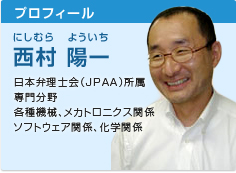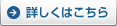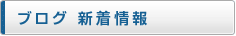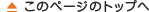第9回 商標の類否判断(3)
2013.09.04 10:00
今回は二以上の語、図形または記号の組み合わせからなる商標(これを、「結合商標」といいます。)の類否判断について説明します。
商標の審査基準には、「結合商標の類否の判断は、その結合の強弱の程度を考慮し、例えば、次のように判断するものとする。ただし、著しく異なった外観、称呼又は観念が生ずることが明らかなときは、この限りではない。」と規定されており、具体例としては、7つのパターンが挙げられています。
商標の類否判断は、基本的に商標を構成する全体の文字等により生ずる外観、称呼または観念により行うのが原則です。しかし、結合商標については、その結合の程度が弱い場合は、分離して類否判断するということです。
二以上の語の結合の状態は、以下点を考慮して認定されます。
①構成上一体であるか
②全体の構成から一定の外観、称呼又は観念が生ずるか
③自他商品の識別力を有する部分とそうでない部分がないか
④一部に特に需用者に印象づける部分がないか
⑤称呼した場合淀みなく一連に称呼しうるか
つまり、これらが否定されるときは、結合の程度が弱く、識別力を有する構成の一部(要部)をもって取引きに使用される場合が少なくないからという理由で、一部を分離ないし抽出して類否判断がなされることになります。
なお、自他商品又は役務の識別力が強くない語同士の結合の場合は結合の状態が強く、一連に称呼、観念されるのが経験則であるとする判例があります(平成14年(行ケ)266号 東京高平成15年1月21日 速報334-11278)。
次回は、審査基準に挙げられている具体例について説明します。
弁理士 西村陽一