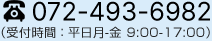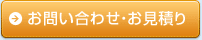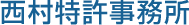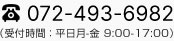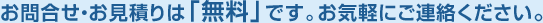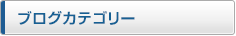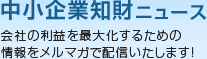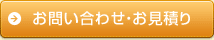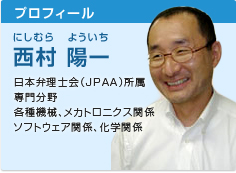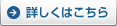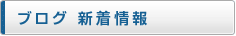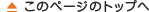第8回 商標の類否判断(2)
2013.08.28 10:00
第7回の「商標の類否判断(1)」では、商標の有する「外観」、「称呼」及び「観念」といった判断要素について説明しましたが、今回は、商標の類否判断を行う判断主体についての基準を説明します。
商標の審査基準には、「商標の類否の判断は、商標が使用される商品又は役務の主たる需要層(例えば、専門家、老人、子供、婦人等の違い)その他商品又は役務の取引きの実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならない。」と規定されています。
1.「取引きの実情」とは、以下に示すようなことを意味しています。
・需要者の範囲(「専門家(商品が原材料)」か「一般消費者(商品が最終製品)」か)
・商品の流通経路(例えば、商品の販売主体が専門業者か一般小売業者か)
・商標の採択の傾向(例えば、薬剤は「ドイツ語」、化粧品は「フランス語」等)
・商標の使用状態(取引きが商標より生ずる称呼によるのか、全体構成の外観によるのか)
2.「需要者の通常有する注意力」
「需要者」には、取引者及び一般消費者の双方が含まれ、「取引者」とは、当該商品の製造・販売または役務の提供に従事し、一定の商品や役務の知識を有する者を言います。
そして、商標に払われる注意力は商品や需要者によって異なるので、それぞれに応じた注意力を基準にして判断するということです。
・子供は、欧文字や漢字の違いは分かりにくいが、図形やキャラクターの違いは見分けやすい
・安価な使い捨て商品と高価な耐久商品とでは注意力が異なる
・一般消費者が払う注意力と専門家が払う注意力とは異なる
・注意力が散漫な者や慎重な者は基準とならない
弁理士 西村陽一